Home > Archives > 2014年7月 Archive
2014年7月 Archive
アカメガシワの若い実
- 2014年7月31日 21:54
文月、最後の日、きょうも36度と猛暑日でした。
ふーっ(^_^;;)。
先日行った池の周りにアカメガシワの木がありました。
たまたま、目線にこんなものが・・。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
アカメガシワの若い実でした。
初めて若い実を見ました(*^^)v
(雄花や黒い実は見たことがあるのですが、まだアップしてませんね~、
すみません^^;)
アカメガシワは雌雄異株です。
これは雌株ですね。
花は5月の終わり頃から咲き始め、7月末には若い実ができるようです。
白っぽい緑色のひとつひとつの実は扁球形で、赤褐色がっかた雌しべの
柱頭は3~4つに分かれていました。
白緑色の実は粉が吹いたように見えますが、腺点だそうです。
腺点とは蜜、油、粘液などを分泌または貯めておく小さな点のことです。
周りには刺状の突起のようなものも付いています。
ちゃんと手で触って来ればよかったのですが、ハチが盛んにこの実に
出入りしていたので、できませんでした(x_x)。
本州(秋田県以南)、四国、九州、南西諸島に分布します。
トウダイグサ科の植物です。
過去記事はこちら→ アカメガシワ
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
セダカシャチホコの幼虫
- 2014年7月28日 09:29
- その他
おとといの土曜日、連れ合いが中学生の時に釣りによく行った
という池に、初めて訪れました。
おおよそ半世紀ぶりに訪れた池はもちろん、周囲の環境も激変し、
感慨深げな連れ合いでした。
カンカン照りの日で、やや前に刈ったかと思われる草の山に、
容赦無く直射が照りつけていましたが、コシアキトンボが2匹、
元気に回旋していました。
日向と日蔭のコントラストの差が大きく、樹木が濃い影を
落としていたのが印象的でした。
さて、影に入った茂みで、水色っぽいイモムシをいきなり発見!
申し遅れましたが、きょうは虫嫌いの方にはご遠慮願いたく
存じますm(_ _)m
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
こんな色のイモムシは初めて~。
だんだん上へ登っています。
大きさは4~5センチ程でした。
帰宅して、最近買ったイモムシハンドブックで調べたら、
「セダカシャチホコ(背高鯱鉾)」でした。
シャチホコガ(鯱鉾蛾)のひとつです。
尾張名古屋は城でもつ♪・・名古屋城の金の鯱鉾♪
鯱鉾つながりで・・^^v
幼虫の食草はクヌギやアベマキ、コナラなどブナ科の植物だそうです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ヘビウリの花
- 2014年7月26日 16:48
皆様、暑中お見舞い申し上げます。
昨日は38.2度、きょうも37度と猛暑、猛暑のこちら名古屋です。
ふ~(^_^;;)。
うだる暑さですので、戸外での撮影も30分程で汗が目にしみ退散(∋_∈)。
さて、先日、思いがけずヘビウリに再会しました^^。
眼の前にくねくねとした細い実がぶら下がっていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
あっ、ヘビウリだ!とすぐに思い出しました。
ずーっと見ていくと、あっ、花が咲いていました。
艶のない葉は互い違いに付いて、掌状に裂けています。
ヘビウリの花はカラスウリの花とそっくりです。
ウリ科の植物です。
是非、過去記事もご覧下さい。
過去記事はこちら→ ヘビウリ
参考:カラスウリの実
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
バライチゴ
- 2014年7月19日 09:07
今朝も梅雨空、朝から雷鳴が聞こえました。
庭からクマゼミの大合唱が聞こえてきます。
階段に落ちていたケヤキの小枝を拾って見たら、緑色の小さな実が
付いていました。
きょうは山の斜面に咲いていた「バライチゴ」をお届けします。
「薔薇苺」と書きます。
別名は ミヤマイチゴ(深山苺)というそうです。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
山地の日向に映える落葉小低木で高さ20ー50センチ程。
茎には毛がなく、下向きに曲がった刺があります。
触るととても痛いです。
小葉は2~3対つき、長さ3~8センチ程で細長く、縁には尖った
二重のギザギザ(細かいギザギザが二重にある重鋸歯)があります。
葉裏は白っぽい。
花は大きく、直径4センチ程ありました。
ガク片の先は尾状に長く尖っています。
西洋蜜蜂がやってきました。
花期は 6~7月 です。
本州(関東地方以西)、四国、九州 に分布します。
バラ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
サワギク
- 2014年7月16日 08:12
朝からお天気が良く、陽が昇って小一時間程でクマゼミの大合唱と
あいなりました。大音量で~す・゚>>>^_^<<<゚・
花瓶に挿したグロリオサやオンシジゥムに交じり、カサブランカが
次々と咲き、強い香りを放っています。
さて、面の木峠の谷筋に黄色の菊が咲いていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
沢沿いなどの湿り気のある場所に生える「サワギク」でした。
「沢菊」と書きます。
草丈は1メートル前後でした。
葉は深く切れ込んでいます。
アップで・・。
柔らかい風情で生えています。
6月から8月にかけて黄色い花を咲かせるようです。
葉裏はやや白っぽかったです↓
実が稔ると冠毛が集まって、ぼろくずのように見えるので、
ボロギクの別名もあるそうです。
北海道から九州に分布します。
キク科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
サンカクヅルの花
- 2014年7月12日 19:46
台風も去り、日本列島はきょうは晴れの所も多いとか・・。
遅まきながら、台風の被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。
私の方では被害もなく、今朝は早くからセミの大合唱に加え、
キリギリスの鳴き声も聞こえています。
こちらのきょうの気温予測は35度超えとのこと・・。
さて、きょうも面の木峠の途中で出あった植物をお届けします。
林縁を歩いていたら、サンカクヅルに出あいました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
よく見たら花が咲いていました。
円錐形で淡黄緑色の小さな花が付いています。
花だけでなく一部は若い実になっていました↓
雌雄同株です。
本州、四国、九州に分布します。
過去記事はこちら→サンカクヅル
ブドウ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ウラジロマタタビ
- 2014年7月10日 17:00
台風がもうすぐこちらへ来そうです。
ベランダの植木鉢など避難させましたが、たまに結構強い風が
音をたてて吹くものの、雨は降ったり止んだりで蒸し暑いです。
今夜がピークかな?
さて、面の木峠に向かう途中、つる性の茂みの中に
何やら白い花がちらっと見えました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
よく見ると、白い花がいっぱい!
実ができているのもありました。
風が吹いて揺れてしまい、ピンボケですが・・^^;
左手前の裏返った葉が白っぽいですね。
葉の裏が白っぽいので「ウラジロマタタビ」でした。
「裏白木天蓼」と書きます。
きょうはこの「ウラジロマタタビ」をお届けします。
マタタビの名が付いていても、マタタビではなく
サルナシの変種だそうです。
やや厚い皮質の葉は互い違いに付いており、
葉の縁には刺状のギザギザがあります。
葉柄は長く、淡紅色を帯びています。
落葉つる性の木です。
5枚の花びらの白い梅のような花は直径1~1.5センチ程。
雌雄異種です。
雌花は葉の脇から1個ずつ付くそうです。
雄花や両性花は数個集まって付いています。
↑これは雄株で雄花が付いています。
雄しべは多数で、葯は黒色なんですね~。
↑これは両性花で、花柱は線形で多数、放射状に出ており、
花後も残っています。
関東以西~九州の山地に生えます。
マタタビ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
アワブキ
- 2014年7月 7日 21:55
梅雨空の中、きょうは朝からマンションの樹木の剪定、
庭師さんの電動バリカン?の音が響いていました。
さて、先日出かけた面の木峠に行く途中のこと・・。
雨がパラパラしだした山道を行くと、あっ、白い花が咲いている木が・・。
連れ合いが「あ、アワブキだ!」とのたまう。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
確かに「泡吹」の名の通り、遠くからは白い泡がかぶさったように
見えました^^。
しかし、帰宅して調べたら・・、
この木を燃やすと切り口から泡を出すので名付けられたそうです。_(・_.)/ コケッ。
山地に生える落葉高木です。
高さは10メートル程になるそうです。
樹皮は灰褐色でなめらかそうでした。
若い枝はブツブツと隆起した皮目(ひもく)が目立っていました。
葉は互い違いに付き、長さ10~25センチ程の倒卵形~楕円形。
葉の先はキュッと尖り、2~2.5センチ程の葉柄があります。
葉の縁にギザギザがありますが、低くて先の方だけがツンツンと
突き出した芒になっています。
側脈が平行にギザギザの凸部の先まで綺麗に走っているのが目立ちます。
葉の両面に毛がありましたが、表より裏に毛が多くあり、
共に脈上に毛が多かったです。
葉柄にも毛がありました。
6月~7月に枝の先に20センチ程の円錐形の塊りの花を付けます。
1つ1つの花は直径2~3ミリ程の小さな淡い黄白色の花です。
花びらは5枚で外側の花びら3枚は広卵形、内側2枚は線形です。
本州、四国、九州に分布します。
アワブキ科 の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ナスの収穫
- 2014年7月 6日 16:33
昨日の朝、クマゼミの初鳴きを聴きました。
もう少ししたら、梅雨明けかな・・。
さて、輝くばかりの紫黒色の肌が魅力!
って、何のことか?わかります??
正解は「ナス」。
きょうはこの「ナス」をお届けします。
キュウリと同じ日にベランダの大きめの鉢に一苗を植え付けたものです。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
俗に「ナスに無駄花はない」といわれますが、実際にはかなり
落花がありました^^;
採れたては、実がつやつやしており、張りがあり、ヘタについている
トゲがチクチクするほどしっかりしています。
我が家のは「千両」という品種です。
収穫第1号は13センチ程ありました。
ナスの実の皮はツルツルピカピカですが、葉や茎、ガクには
星状毛(一カ所から多方向に分岐して放射状になっている毛)が
あります。
葉裏↓
茎↓
ヘタには鋭い棘があり、私も昔、刺がささった経験があります、
メチャ、痛かった~!ご注意下さい。
昔から、縁起のいい初夢として「一富士、ニ鷹、三茄子」と言いますが、
「茄子は成すに通じる」ことから茄子は縁起物として扱われます。
古くからなじみのある、夏の代表的な野菜ですね。
焼きナスを初め、塩もみ、油炒め、テンプラ、漬物、味噌田楽など・・
いいですネェ。
英語ではナスはエッグプラントと呼ばれ、卵形や丸形もあり、
実の形や用途も多彩ですが、以下に代表的なものをあげてみます。
小なす-3センチ程の小さなナスで、辛子漬けなどに使用。
丸なす-丸くて大きい、京都の賀茂ナス。
長なす-仙台ナスは極細長で先端が尖っており、皮が柔らかい。
あと、大阪府泉州の水ナスなどもありまね。
そうそう、昔から「秋ナスは嫁に食わすな」といいますね。
これは、ナスは食べると体を冷やす効果があるので、
大事なお嫁さんが体を壊さないように、
秋になって涼しくなったら、体を冷やすナスは食べさせるな、
という気遣いから来ているそうです。
原産地はインドです。熱帯植物です。
天平勝宝2年(750年)東大寺正倉院文書にナス献上の記事があるのが
日本最古の記録とか・・。
「倭名類聚鈔」では「奈須比(なすび)」という字をあてていたそうで、
あとに宮中の女房言葉で「なす」となり、それが広まって現在に・・。
漢名は茄子、別名は落蘇、崑崙紫瓜というそうです。
日本人好みの淡白な味は江戸時代から促成栽培が行われるほど、
重要な野菜だったらしい。
ナス科の植物です。
過去記事はこちら→シロナス
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
オニタビラコ
- 2014年7月 4日 09:46
昨日は雨がしっかり降りましたが、きょうは雲間から
薄日も時々射しています。
アオスジアゲハが飛んでいます。
なぜか?コシアキトンボの姿は見えません。
さて、きょうは「オニタビラコ」をお届けします。
「鬼田平子」と書きます。
タビラコに「オニ」(大きい意味)という接頭語が付き、名付けられました。
ちなみに、田平子とは、葉が田の面に放射状に平らに広がることから
"田平"子となったようです。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
茎が高く伸び、道端で普通に見かけます。
一見、控えめに見えるオニタビラコですが、栄養分の多い場所では
株立ちとなって、高さ1メートル程の高さになるようです。
日本全国のみならず、世界に広く分布しているそうです。
キク科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0















































 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

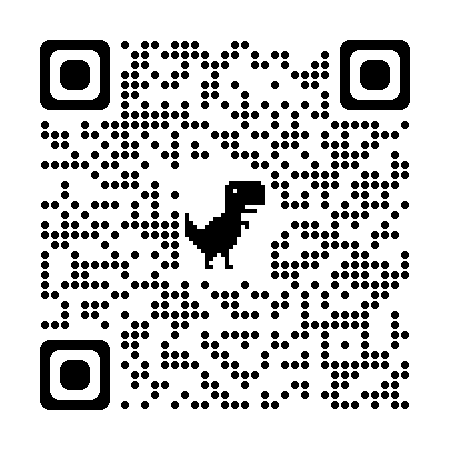 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







