Home > Archives > 2011年1月 Archive
2011年1月 Archive
オオカメノキの冬芽
- 2011年1月31日 11:12
- 冬芽
朝起きたら、また、家々の屋根や木々の葉がうっすらと雪化粧。
今はまた鈍色の空から雪がチラチラと・・。
今年はよく雪が降ります^^;
きょうは先日撮れたオオカメノキの冬芽をお届けします。
「大亀の木」と書きます。
葉の形が亀の甲羅に似ているので名付けられました。
別名は葉が虫によく食べられることからムシカリともいいます。
ムシカリの花と最初に出逢ったのは、数年前の5月の鈴鹿だったと
思いますが、今でもあの白い花が忘れられません・・。
さて、今回オオカメノキの冬芽を初めて撮りましたが、
花芽と葉芽があります。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
花芽は真ん中ので、球形をしています。
葉芽はVサイン。
花芽のアップ↓
表面には褐色の毛が密生しています。
両側に伸びる羽のようなものは葉芽です。
幼い2枚の葉が向き合っており、葉脈が見えます。
バンザ~イしてるような姿。
また、この写真では、まるで幼い羊?のような顔にも見えます↓
北海道~九州の山地に分布します。
スイカズラ科の植物です。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
トチノキの実
- 2011年1月27日 11:02
- 木の実
今朝、家々の屋根にうっすらと雪が積もっていました。
今年は庭の木の実が早くなくなるとのこと・・そう知り合いから
聞きました。
山の木の実が少ないのか?今年は早くに鳥が里まで降りてきて、
ついばんでしまうからなのかしら?
さて、きょうは人の食用にもなる「トチの実」をお届けします。
トチの実↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
縄文時代から食べられていたと言われます。
文字通り、栃の木に成る実です。
トチノキの実はデンプンやタンパク質を多く含みます。
見た目がクリの実にそっくりですが、なかなかそう簡単に食べられる
ようにはなりません。(大きさは大きめの栗くらい)
実には苦味や渋みの素のタンニンやサポニンが含まれているので、
これらを取り除かないと食べられません。
トチの実と殻↓
栃の実を何日も水に晒して皮をむき、灰汁を抜くなど多くの工程と
日数をかけて、やっともち米と共についた栃餅や栃の実煎餅などが
できあがるようです^^;
どんな動物がトチの実を食べているのかな?ってちらっと思いました。
また、数年前に伊那の温泉に行った時、土産物コーナーに栃の実煎餅が
おかれていたのを思い出しました^^。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ハナミョウガの実
- 2011年1月23日 17:54
- 草の実
きょうはお年玉年賀葉書の当選番号が発表されましたね。
皆さん、当たりましたか?
私は、今年やっと2年ぶりに一枚だけですが当たりました^^。
もちろん、切手シートがね♪(笑)
さて、林の縁に倒れ掛かった大きめの葉の影に赤いものが
チラッと見えました。何かな?と少し葉をどけると・・
ハナミョウガの実のようでした。
きょうは「ハナミョウガの実」をお届けします。
「花茗荷」と書きます。
葉や茎がミョウガに似ていて、花が目立つので名付けられました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉の影に隠れてた真っ赤な実は径1センチ程でした。
草丈は40~60センチ程でした。
葉の幅は5~8センチ程、葉の長さは15~40センチ程で、
少しハランの葉に似ています。
実は秋から冬に赤く熟し、花は6月に咲くそうです。
関東以西~九州に分布します。
ショウガ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ムサシアブミの実
- 2011年1月19日 12:16
- 草の実
マンションの植木鉢にはまだ少し雪の塊が残っています。
その中からピンクのガーデンシクラメンが半開きで、けなげに
頑張って咲いています。
実家の庭のニホンズイセンも雪の中から蕾を少し開いていました。
さて、きょうは「ムサシアブミの実」をお届けします。
林下に「武蔵鐙」の実がまだ付いていました。
2本の茎の間にある独特の形をした花(仏炎苞)の形が、昔、
武蔵の国で作られた鐙(馬に乗る時の足置き)に似ているので
名付けられました。
まだ、三つでひとつの葉があるうちは、実は緑色でした(11月)↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
実が赤く色付く頃になると、実の重さで地面に倒れてしまいます(1月)↓
テンナンショウ、ウラシマソウ、マムシグサなど、この仲間は
実だけでは種類を見分けられないので、花や葉があるうちに
要チェックですね。
関東以西の本州~琉球に分布します。
サトイモ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ヒトツバ
- 2011年1月16日 09:31
- シダ植物
昨夜はとても寒く、今朝一番に目にした光景は?!
ひゃぁ~ヾ、道路の脇に残った雪!
マンションの庭園の木々の葉もうっすらと雪化粧・・でしたが、
今は雪がたえまなく降ってきて、花壇も真っ白に覆われました。
きょうもセンター試験ですね。受験生の皆さん、頑張れ~!!
さて、きょうは実家にも生えていた「ヒトツバ」をお届けします。
ヒトツバは、本来、暖地の乾燥した岩の上や樹幹に群生する
ことが多い、常緑のシダ植物です。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉は立ち上がり気味で、高さ30~40センチ程です。
葉はやや硬い革質で厚みが多少あります。
葉の表面↓
葉の裏に胞子のうが付いている葉と付いていない葉がありました。
葉裏に胞子のうが付いていない葉↓
葉の裏は毛が密生しており、灰褐色でした。
また、胞子のうが葉裏全体に付いているものと、葉裏の一部にしか
付いてないものがありました。
胞子のうが葉裏全体に付いているもの↓
葉裏の一部にしか胞子のうのないもの↓
胞子のうがたくさん付いた葉ほど、柄が長く、葉の幅が狭くなる
そうです。
関東以西の本州から琉球列島に分布するそうです。
ウラボシ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ヤブランの実
- 2011年1月13日 10:05
- 草の実
寒い日が続きますが、植物の冬芽は春への準備に怠りがないようです。
さて、きょうは、夏にたくさんの紫色の小花で楽しませてくれた
ヤブラン(藪蘭)がまだ実を付けていたので、「ヤブランの実」を
紹介したいと思います。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
はじめ、緑色だった実がだんだん熟して黒紫色となり、
艶々と輝いている姿はとても綺麗です。
関東以西の温暖な地に分布する常緑の草です。
名前のとおり樹木の下などの薄暗い、いわゆる藪に自生していますが、
古くから庭に植栽されてもいます。
ユリ科の植物です。
花はこちら→ ヤブラン
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
植物園初詣で
- 2011年1月12日 08:02
- その他
新年が明けてはや10日も過ぎ、きのうは鏡開きでしたね。
三連休にやっと恒例の植物園初詣でが出来ました。
きょうは、初春の植物園風景をお届けします。
今年の干支のウサギ↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
白のパンジーで現わされた2匹の兎が見えますか?
スカイタワーと温室をバックに・・↓
寒い日で池の一部では厚い氷が張っている所もありましたが、
侘び助などのツバキが咲き、ソシンロウバイも
馥郁たる香りを放っていました。
ダイダイ、ユズ、ナンテン、フユイチゴ、カンアオイ、
ハナミョウガ、ムサシアブミの実なども見られました。
最後に温室を見てまわり帰路につきました。
久々に東山に行き、リフレッシュできました^^。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
2011年ご挨拶
- 2011年1月 5日 10:27
- その他
皆さま、新年おめでとうございます。
fabも六度めのお正月を迎えることができました。
これも皆様のご声援のおかげと感謝しております。
どうか今年もfabをよろしくお願いいたします。m(_ _)m
さて、きょうはご挨拶とともに「しめなわ」をほんの少し、
ご紹介しましょう。
「注連縄」と書きます。難しい字ですね^^;
皆さんも飾られたかと思いますが、お正月に玄関や出入り口などに
飾る注連飾りも、注連縄の一形態であり、厄や禍を祓うお守りの
ようなものでしょうか。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
この注連縄は片側のみが細いので牛蒡じめのようですが・・。
他に、両端がつぼまるのは大根じめというそうです。
注連飾りは玄関に飾るのを玉飾りと呼び、台所やトイレなどに
飾るのは輪じめと呼びます。
地域によって違いますが、このように縁起物である紙垂(しで)、
ダイダイ、裏白などがいっしょに飾られます。
- Comments: 3
- TrackBacks: 0






















 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

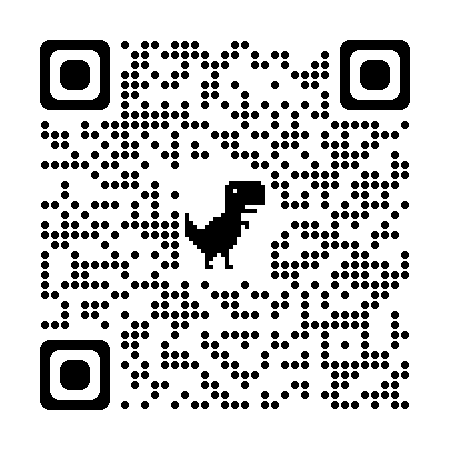 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







