Home > Archives > 2009年3月 Archive
2009年3月 Archive
室内の桜
- 2009年3月29日 17:39
- その他
桜が咲き、花冷えが続いていますが、皆様お変わりありませんか?
きょうはちょっと寂しいですが、部屋の中の桜をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
もう、ひとつ・・。
きょうは旧暦の雛祭りの日ですね。
まだ、お雛様、飾っています。
でも、お雛様ともそろそろお別れです。
弥生三月は別れの季節でもあります・・。
- Comments: 7
- TrackBacks: 0
ウズ
- 2009年3月24日 14:47
- 花
マンションにあるケヤキが、ここ数日ですごい勢いで
芽吹いてきました。
きょうはそのケヤキのそばにある「雲珠(ウズ)」という
椿をお届けしましょう。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
「ウズ」は、花びらが中心に向かって、まさに渦を巻く
ように咲きます。
薔薇のような八重咲きです。
しべのつき方にも特徴がありますね。
直径6~6.5センチ程の中輪です。
濃いピンク色が愛らしいです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
初桜
- 2009年3月21日 08:40
- 花
きのう、駐車場に行く途中、ふと空を見上げたら、
マンションにある桜が今年初めての花を咲かせていました。
すぐにカメラを出して撮りました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
アップで・・。
マンションに来るウグイスも、おとといから自慢の声を聞かせてくれて、
いよいよ春満開の気配です^^。
- Comments: 6
- TrackBacks: 0
ヤマネコノメソウの花
- 2009年3月18日 18:19
- 花
きょうはきのうにも増して暖かい一日でした。
また、また、ネコノメソウの仲間のお話です。
去年、実が付いていたヤマネコノメソウは見ましたが、
念願の花を偶然にも渓流沿いで見ることができました^^。
きょうはこの「ヤマネコノメソウの花」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
茎と葉の柄にはまばらに柔らかい毛が生えていました。
葉の縁にはゆるいギザギザがあります。
茎の間に付く葉は1~2枚で、互い違いに付いています。
花は直径5ミリ程、4枚の花びらのように見えるのはガクで緑色です。
雄しべは4~8本です。
北海道~九州の林の縁や湿った土手などに分布しています。
こちらも是非ご覧ください↓
ブログ内過去記事→ヤマネコノメソウの実
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ネコノメソウ
- 2009年3月17日 17:40
- 草
きょうは暖かい一日でしたね。
きのうの続きで、きょうは「ネコノメソウ」をお届けします。
北海道~本州に分布しています。
田の用水路など水を好み、水辺の中にも生えたりします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉は向かい合って付いています。
ランナー(走出枝)があります。
開花時は上部の苞や葉は黄色味を帯びます。
花後は緑色となるそうです。
花といっても花びらはありません。ガクだそうです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
トウノウネコノメ
- 2009年3月16日 15:08
- 花
きのうは久しぶりに花を見るために市外、かつ県内に外出しました。
もちろん、マスクは欠かせません^^;
里山風景を愛でながら、流れのある所まで来たら、な、なんと、
「トウノウネコノメ」を見つけてしまいました!
わーい!やった~!!
きょうは、この「トウノウネコノメ」をお届けします。
「東濃猫の目」と書きます。
「トウノウネコノメ」は、東濃地方の一部(恵那山麓とその周辺)で
見つかり、1999年に学会で「トウノウネコノメ」と認められた
新種だそうです。
長野県、岐阜県、愛知県に自生しています。
山地にある川沿いに群がって生えていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
湿った所に生えている木のもとにも生えていました。
きっと水分が好きなのですね。
3月~4月に花が咲きます。
花びらはなく、黄色い4枚のガクに囲まれるようにして、
6~8本の雄しべが長く飛び出るのが特徴です。
葉は向かい合って付いています。
また、雌しべの先は真ん中で切れ込んで二つに分かれています。
写真をよく見て~わかるかな?
葉茎には毛がありました。
いいもの見ちゃった~!
自然の恵みをいただき、最高にいい気分の一日でした^^v
- Comments: 6
- TrackBacks: 0
光源氏
- 2009年3月13日 12:41
- 花
きのうは奈良の東大寺のお水取りでしたね。
三寒四温を繰り返しながら、そろそろ本格的な春が来る頃です。
きょうは近所の雑木林で咲いている椿をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
調べたら「光源氏(ひかるげんじ)」という椿でした。
絵巻物に描かれた牡丹のような大輪、バラのようにも見えます。
3~4月に咲きます。
1859年の「椿伊呂波名寄色附」に載っている江戸古種だそうです。
ツバキ科の植物です。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
ポピー その2
- 2009年3月12日 14:58
- 花
また、切花のポピーが咲いてきました。
きょうは、「ポピーの開花」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
もうすぐ、開花しそうな蕾がありました。
この間、23分
この間、1分
あらっ、帽子が飛んじゃった!
この間、1分
ついに咲きました!
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
ポピー
- 2009年3月10日 14:10
- 花
きのうの朝、ポピーの花がポコンと音をたてたかのように
咲きました。
房総半島から送られて来て三日目でした。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
毛むくじゃらのガクの帽子を脱いだ美人さんです^^。
花が咲き始めてまだ完全に開ききってないはいないようです。
咲きたてのホカホカ状態の写真をお届けしました^^。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
ヒメスミレ
- 2009年3月 7日 11:18
- 花
今朝、床の中でウグイスの地鳴きを聴きました。
雨が上がって風がかなり吹いています。
きょうはいつのまにか、ベランダに住んでいた住人?
「ヒメスミレ」を紹介します^^。
「姫菫」と書きます。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
人里近くによく見られますが、このように日当たりのいい
ベランダや芝生の中、アスファルトの割れ目や石垣の隙間、
砂利道の縁などにも出没します^^。
濃紫色の小ぶりのスミレです。
花の横幅1センチ、縦幅は1.5センチ程でした。
横の花びらのもとに毛がありました。
地面近くに葉を広げています。
葉の縁にはギザギザもありますね。
葉裏が紫がかっているのもあります。
蕾もいくつかありました^^。
本州~九州分布に分布します。
スミレ科の植物です。
- Comments: 8
- TrackBacks: 0
水玉 その2
- 2009年3月 6日 15:56
- その他
やっと雨があがったようです。
きょうは雨上がりのベランダの様子
をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
ヒヤシンスに水滴が・・。
手すりにも水滴が・・。
こっちにも・・。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
見つけた!
きょうは「ひな祭り」でしたが、雪がふったりして、
我が家のお雛様も寒そうでした。
さきほど、おそなえしてあった「おこしもん」を焼いていただきました。
近くの雑木林にスイセンが咲いていたので撮ったら、
偶然キジバトが写っていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
公園のサクラの木に、キジバトがこんな姿をして
止まっていましたよ。
きょうは本当に寒い一日でしたね。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ベニボクハン
- 2009年3月 2日 16:07
- 花
車窓から信号待ちをしながら街路樹を見ると、コブシの花が
開きかけていました。
また、春らしいパステルカラー(菫色の濃淡)に身を包んだ
色白の彼女を見かけました。
この3月弥生の時期は風が強い日が多いので辛いですが、
春のファッションを先取りした人を見るのは嬉しい気がします。
さて、きょうは私のマンションにある「ベニボクハン」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
ツバキは万葉集にも登場し、室町時代には茶花として愛用され、
江戸時代には将軍や大名が庭に植えて愛でたとのこと・・。
「紅朴半(べにぼくはん)」です。
「日光(じっこう)」、関東では「紅唐子(べにからこ)」とも呼ばれます。
1739年(江戸時代中期、徳川吉宗の時代)の「本草花蒔絵」という
書物に、「唐子」として載っている古い品種だそうです。
唐子咲きで特徴があります。
今年は早く咲き始めました。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
パフィオペディラム・ミクランサム
日差しが春めいてきましたね・・。
紫のヒメスミレがベランダで咲いています。
きょうは蘭展にあった「パフィオペディラム・ミクランサム」
をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
本来は、中国の雲南省の標高1000メートル程の山地の
石灰岩の岩場の裂け目等に苔と共に生えているそうです。
岩の割れ目に根を伸ばして、匍匐茎から新芽を出し、
茎の頂に一つだけ花を付けます。
花期は2~5月だそうです。
最低温度が4度近くまで下がる涼しい環境で育つそうです。
自然の中でこの花を見たら、感激もひとしおでしょうね・・。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0




































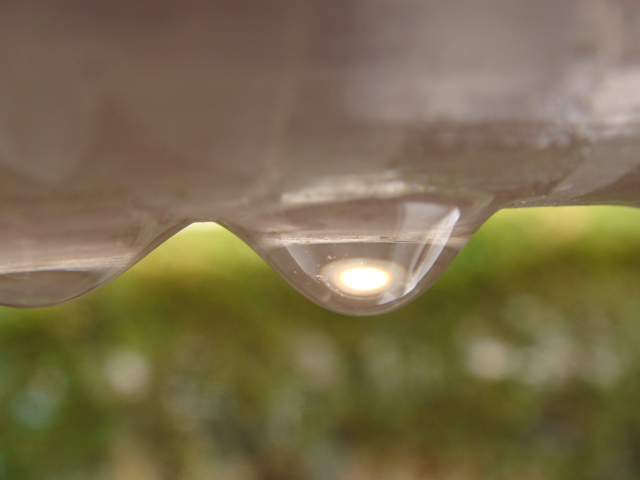










 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

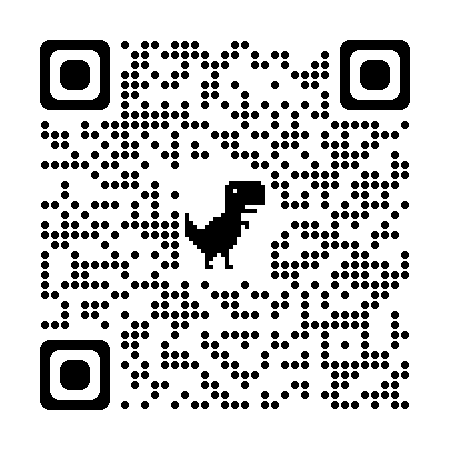 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







