Home > Archives > 2013年6月 Archive
2013年6月 Archive
エビヅル
- 2013年6月29日 10:58
- 木
梅雨の晴れ間、ベランダで木立ベゴニアの花が咲いています。
玄関では、月下美人に小さな蕾が付いているのをきのう発見しました^^。
きょうは里山の林の縁にあった「エビヅル」をお届けします。
「海老蔓」と書きます。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
丘陵から山地の林縁などに生え、巻きひげで他の樹木などに
絡みついて伸びます。
葉は互い違いに付き、長さは5~15センチ、幅は5~10センチで、
浅く3~5つに裂けます。
葉の縁には疎らに浅いギザギザがあります。
雌雄異株です。
どちらも6~8月頃、黄緑色の小さな花を咲かせます。
雄花には雄しべが5本あり、雌花にも雄しべが5本と雌しべが
1本あるそうです。
雌株は柱頭が目立ち、その周りに短い雄しべが飾りのように
つくそうです。
花びらは帽子のような形をしているそうですが、残念ながら
早々と咲き落ちてしまったようです。
これは雌株なので雌花がつき、雌しべだけになっていました。
葉は秋には紅葉します。
そして実は球形で黒く熟し、食べることができるそうです。
本州、四国、九州に分布します。
ブドウ科の植物です。
きょうはいつもfabをご愛顧して下さる皆様に特別大サービス!\(^o^)/
こっそり!?おまけとして「エビヅル」の見分け方の極意を
お教えしちゃいます(^┰^)ゞ テヘヘ
☆葉をそっと裂いてみて下さい。
"エビヅル"なら切り口に糸ひくような毛が見えます。
これが"エビヅル"の動かぬ証拠です( ^-^)σ[]ぴんぽーん!
これでバッチリ!あなたも植物見分けの達人です~(≧∇≦)ъ グウッ!
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ママコノシリヌグイ
- 2013年6月24日 11:22
- 花
ここ2~3日前からベランダでキリギリスのような声が聞こえます。
明け方まで雨が降っていましたが、今は止んでいます。
梅雨空で、動くと暑く汗もしたたり落ちますが、陰で休んでいると
汗も引き、風が心地よいです。
きょうは「ママコノシリヌグイ」をお届けします。
「継子の尻拭い」と書きます。
茎に下向きの鋭い棘を持ち、継母(ままはは)が継子(ままこ)
のお尻をこれで拭いて、継子いじめをする例えで名付けられたようです。
花はソバの花に似て、棘があるので別名はトゲソバだそうです。
流れや池の周辺など湿り気のある所に生えています。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉は三角形で、茎はつる状になり、四角ばっていました。
花はミゾソバによく似ています。
開いた花↓
北海道~九州に分布します。
タデ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
アシダカグモ
- 2013年6月22日 08:39
- その他
きのうまで洗濯はおあずけ、今朝、やっと青空が見えました^^。
でもまだベランダの手すりには雨粒が付いたまま・・。
きょうも古い写真ですがお許しを・・^^;
今年2月1日の朝、部屋の中で発見!
クモ嫌いの方にはごめんなさい。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
部屋のどこかで越冬中だった?が・・
昼夜を間違えて壁伝いに出てきてしまったのか?
写真を撮らせてくれた後、足早に冬眠中の場所へ戻って行った?らしい。
調べたところ、アシダカグモ(脚高蜘蛛)という名で、ゴキブリの
天敵という"益虫"で、無毒でおとなしいクモだそうです。
屋内で見かける大きなクモで、5年前後の寿命だとされています。
帰化種で、分布の中心は熱帯・亜熱帯地域だそうです。
日本での生息地は、茨城県以南の本州、四国、九州の人家とのこと。
また、日本に生息する網を張らない徘徊性のクモとしては最大だそうです。
姿を現したクモは3~4センチ程でしたが、大きいものでは足を広げた
大きさがCD1枚分程のアシダカグモもいるそうです~∑(=゚ω゚=;) マジ!?
暗い所でガサッと音がしたり、大きなサイズのクモが顔の上に現れたら、
さすがに心臓に悪いですが・・。
そういえば思いだしました。
昔、お寺のトイレに入ったら、ゴムでできたようなホントに大きなクモ
がいて、脂汗もので体は硬直状態でしたヾ(≧Д≦*)ゞ 。
あれはいったい何グモだったのかな?
ひょっとしてアシダカグモ?!
さて、私め、数年前からクモの巣の模様の美しさに目覚め、
クモを見直しました。
ちなみにクモの巣模様付きTシャツ、持ってま~す♪
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
ニワハンミョウ
- 2013年6月20日 07:52
- 虫
梅雨の中、ザ・フェアリーが 2輪咲きました。
この頃、取材に行けてないので、植物ネタでなくてごめんなさい。
きょうは虫嫌いの方にはご難ですが、虫にお付き合いくださいヾ(^^;)
それは日当たりのよい砂地の空き地に見られました。
光沢がない黒っぽい色の目立ちにくい虫が、すばやく
動きまわっていました。
(写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
動きや虫の形から、あ、ハンミョウかも?と思いました。
よく見ると上翅に白い小さな紋がありました。
でも、以前に見たハンミョウとは違い、地味な色です。
さっそく調べると「ニワハンミョウ」でした、
人家のまわりから山地まで、広い範囲で見られ、
個体の数も多いそうです。
地面を動き回り、他の虫を捕らえて食べるようです。
この写真は5月に撮りましたが、4~10月に出現するようです。
北海道、本州、四国、九州 に分布します。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
コナアカミゴケ
- 2013年6月18日 05:07
- 地衣類
オリヅルランの花が咲きました。
白く可憐な花は夕方には閉じます。
きょうは古い写真ですみませんが、この5月の連休に里山へ
出かけた時に発見した地衣類をお届けします。
荒地の岩肌に、赤いマッチ棒のようなもの、見っけ!
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
最初、苔かな?小さなきのこかな?と思ったのですが、
帰宅して調べたら「コナアカミゴケ」のようです。
「粉赤実苔」と書きます。
でも、コケという名前が付いていますが、苔では
ありませんでした_(・_.)/ コケッ。
藻類と菌類とが共生する「地衣類」に属するそうです。
1つ1つの赤い実は直径で2~3ミリ程の「子器」(しき)
と呼ばれる部分で、この中に胞子が作られるそうです。
1つの子柄(長さ1~3センチ程)に赤い実が1つなので
「コナアカミゴケ」としました。
間違っていたら、教えて下さいm(_ _)m。
アカミゴケの仲間です。
本州、四国、九州、沖縄に分布します。
ハナゴケ科だそうです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ザミオクルカス・ザミーフォリアの花
- 2013年6月14日 11:28
- 花
実家のクチナシが咲きました。
そして、一時はこれで今年は終わりか?と思ったバラ、
ミスティー・パープルがまた次々に咲いてきました。
ユキノシタの花は終わり、ピンクのアジサイがたくさん咲いてきました。
つまり、実家の庭はアルカリ性土壌ということですね。
また、マンションではサツキツツジは終わりましたが、
ベランダのレモンに花が咲きました。
卵を産みつけようときょうもレモンの葉に、アゲハ蝶等が
頻繁に来ています。
さて、5月はじめのことですみません^^;
ザミオクルカス・ザミーフォリアの根元に
皮をかぶった花はオモトのような?、そして姿はニョロ~っと
したものが付いている(画面左側手前)のを発見!
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
さっそく調べると、やはり花で、ザミオクルカス・ザミーフォリアの
花でした。
花の部分をアップで・・↓
それから20日間ほど観察していたら、だんだん、苞が
開いてきました。
シメシメ・・と思っていたのですが、
待てど暮らせどだんだん何だか元気がなくなって、
とうとうきのうお釈迦になってしまいました。
フード?(苞)を脱ぐ所を見たかったのですが、残念でした。
ちなみにサトイモ科の植物で、同じ仲間にスパティフィラム
などあります。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ユリの伝統
- 2013年6月12日 10:29
- 本
去年よりユリの開花が早いとか・・、近くの公園では、ユリは
そろそろ終わりがけでした。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
ユリは名古屋の市の花です。
写真のは園芸種です。
さて、きょう、久しぶりに「植物と行事」という本を読んでいたら、
偶然「ユリの伝統」という項目がありました。
なかなか興味深い内容でした。
6月17日に奈良の率川(いざかわ)神社で三枝(さいぐさ)祭りが
行なわれるそうです。
三枝はササユリのことで、このササユリの花を手にした4人の巫女
が舞う神事だそうです。
また、百合根は日本の伝統食料など・・。
あと、ユリの語源等・・。
詳しくはこちらを↓
湯浅浩史著 植物と行事~その由来を推理する~ 朝日選書478
<余談>
ネットで率川神社を調べたら、「いさがわ」神社となっており、
三枝も「さいくさ」となっていました^^;;
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
クヌギエダイガフシ
- 2013年6月 6日 09:36
- その他
梅雨の晴れ間が続いています。
車で走っていてもザクロの朱色の花がよく目に飛び込んできます。
この頃、昼間にふわふわとはかなげに飛ぶ様が蛾と思えない?
黒地に白の鹿の子模様のカノコガをよく見かけます。
さて、1ヶ月程前のことですみません^^;;
5月の連休中に行った雑木林に、茶色の実のようなものが付いた枝が
ありました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
帰って調べると、どうも「クヌギエダイガフシ」のようです。
クヌギエダイガタマバチによって若い枝に作られるそうで、果実と
まちがえそうな形の虫こぶです。
直径1センチ程のほぼ球形で、イガイガの突起が反り返りながら
群生し、この突起には軟毛が密生しています。
触っても痛くありません。
クヌギの枝に出来たイガ状のフシということです。
よく見ると小さな穴が開いていました。
どうもここからクヌギエダイガタマバチが、秋に羽化し、外に出て
いったもようです。
本州、四国、九州に分布します。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
バイカウツギ
- 2013年6月 4日 10:24
- 花
車で近くの公園を通りかかったら、連れ合いが「あれっ?
バイカウツギじゃない?」と言うのです。
気になったので、後から一人でこっそり、もう一度現場に行き
確かめました(笑)。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
ヤブ蚊に献血しながら?いや、命がけでかゆみと戦いながら・・
写真を撮ってきました!!?(x_x) ☆\( ̄ ̄*)バシッ
きょうはこの「バイカウツギ」をお届けします。
「梅花空木」と書きます。
花が梅に似ているから名付けられたそうです。
葉は柔らかな感触で、向き合って付いています。
葉の先は尖って、縁に突起状のギザギザがまばらにあり、
先が禾のようになっています。
テールベルト色の葉表は、ビロードのような感触で、
ルーペで見ると葉脈上にまばらに柔らかな白い毛が生えていました。
灰緑色の葉裏はこんなふうに葉脈が目立っていました。
葉裏は全体に白い柔らかな毛がびっしり生えていました。
径2.5~3センチ程の白い花びらがもう落ちかけているのもありました。
雌しべの柱頭は4つに分かれ、、ガク片の外側には毛が生えていました。
花びらは4枚。たまに5枚、6枚のもありました。
公園に植栽されていたので、園芸種だと思います。
本州(岩手県以南)、四国、九州の山地に自生するそうです。
落葉性の低木で、古くから庭木や生け花の花材としても親しまれていますね。
ユキノシタ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ダイオウグミ
- 2013年6月 2日 13:00
- 木
今年は名古屋も5月28日に早々と入梅宣言がありました。
今朝は早くからカラスやシジュウカラやキジバトの元気な声がして
いましたが、時々パラッと雨粒も・・。
きょうは「ダイオウグミ」をお届けします。
先月、実家に行ったら、幼い頃に思い出のあるビックリグミの実が
なっているのを発見!
もうとっくに絶えたとばかり思っていたのに・・、
うれしくてまだ緑色のその実を≧[◎]oパチリ!
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
そしてその後10日ほどしてまた訪れたら、この間は緑色だった
ビックリグミが真っ赤に熟れていました。
4つあった実が2つしかなくなっていました。
ヒヨドリが食べたのかな?
カメラがなかったので、家に持ち帰り撮影しました。
実は2~3センチの長楕円形。
実が大きいのでビックリグミとも呼ばれますが、本名は「ダイオウグミ」。
「大王茱萸」と書きます。
ダイオウグミはトウグミ(唐茱萸)の園芸種らしいですが、実家では
ビックリグミと呼んでいて、私が小学生の時に父が植えてくれたものです。
大きくて甘い実は妹と競争で食べた記憶があります。
2つとも食べてみましたが、ともに完熟しており、最初少し渋いかな?と
思ったのですが、甘酸っぱい果肉に、皮も薄く溶けるように口の中へ・・。
後はただただ懐かしい甘さが残っただけ・・(#^.^#)。
中にあった種は長さ1.8~2センチ程で、縦の溝が8個ありました。
ダイオウグミの木肌↓
互い違いに付いている柔らかい感触で波打つ葉の表の様子↓
指で葉表を触るとザラついています。
そして、緑色の中に小さな白い星状毛が葉一面に見えます。↓
葉の裏は銀白色に見えます↓
アップにした葉裏はこんなふうでした↓
白や茶色のポツポツ模様が見えますが、鱗状毛のようです。
葉の裏はしっとりした感触でした。
グミ科の植物です。
思いがけず、何十年ぶりかに食べることができ、うれしかったです。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0



































 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

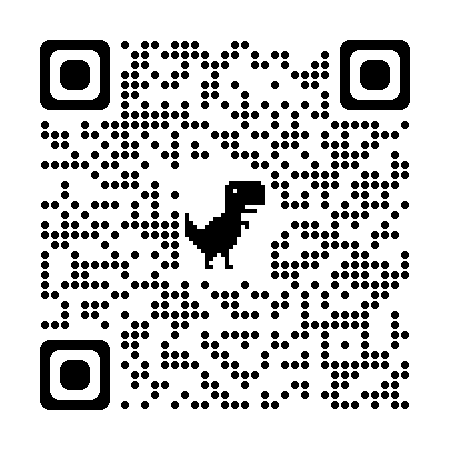 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







