Home > Archives > 2012年10月 Archive
2012年10月 Archive
ツリフネソウ
- 2012年10月30日 21:47
- 花
先週、川べりを散歩していたら、サンシュユの実がもう赤くなって
いました。
マンションのケヤキや桜の葉もボチボチ色づいてきました。
残すところ、10月もあと一日・・。
少し遅くなりましたが、「ツリフネソウ」をお届けします。
じつは「ツリフネソウ」は何年も前から時々写真に撮ったりしてた
のですが、今月初めに三河でも撮れたので、やっとアップする気に
なりました^^;
さて、本文へと・・。
細い花柄から釣り下がる花の姿が、帆掛け舟をつり下げたように
見えることから、ツリフネソウ(釣船草)と名付けられました。
高さは50~80センチ程で山地の湿った場所によく群生します。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉の縁にはギザギザがあります。
これは葉の裏です。↓
花は赤紫色で距(きょ)が後ろに伸び、距の先はくるっと丸まっています。
花の正面はこんなふうです。↓
長さ1~2センチ程の実ができていました。↓
実のアップです。↓
熟した実にちょっと触れたら、あっ、突然、中の種が勢いよく
弾き飛ばされ、後はこんなふうに・・。↓
花言葉は「私に触らないで」だそうです。←なるほど(^m^)
ホウセンカと同じ仲間で、ツリフネソウ科の植物です。
その他、参考になれば→ツリフネソウ
東京都港区白金の自然教育園には行ったことはありますが、
ツリフネソウの季節にはまだ行ってないなぁ・・。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
10月の蝶
朝から雨模様の一日ですね。
秋雨のおかげで、近くの大学祭もイマイチのようです。
今年はキンモクセイの開花が10日ほど遅れました。
実家の垣根のキンモクセイもそぼ降る雨に濡れていることでしょう。
もうすぐ10月も終わり・・。
きょうは10月に見た蝶をお届けしたいと思います。
まずは10月初め三河で見た「アサギマダラ」を・・。↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
サラシナショウマとのコラボです。
お次は10月下旬に名古屋市内で見た「ウラナミシジミ」です。↓
ケイトウとのコラボです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ボダイジュ
- 2012年10月25日 11:19
- 木
一週間ほど前、友達が面白い実を拾ってきたと教えてくれました。
「ボダイジュ」の実でした。
気になっていたのですが、きのうやっと取材できたので、
きょうは「菩提樹」をお届けします。
日本で菩提樹と呼ばれているのは、ほとんどが中国原産の菩提樹で、
シナノキ科の木です。
(お釈迦さまが悟りを開いたのはインドボダイジュの下で、クワ科の木です。)
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
高さは15メートル程ありました。
樹皮には縦に筋が入っていました。
落葉高木です。
木の下には友達がくれた実が落ちていました。
上を仰ぐと、あっ、いっぱい実が・・。
普通の緑の葉に混じって、薄茶色のヘラ形をした葉の裏から
軸が出て、その下に実が付いています。↓
専門用語としては、薄茶色のは葉ではなく「ほう(苞)」だそうです。
「ほぉ~」(笑)
苞には複雑な葉脈模様が見えました。(ちょっと心引かれますぅ~♪)
この苞の中央から、エンドウほどの実がいくつか垂れ下がっています。
次は葉(裏)の写真です。↓
三角状円形の葉は互い違いに付いています。
写真の葉は縦12センチ、横8センチで葉柄は5.5センチありました。
次も葉裏の写真です。↓
葉の縁はギザギザがあり、その先は尖っています。
葉の特徴としては側脈がはっきりしており二次側脈も出ています。
葉を触ると柔らかい感触がし、特に葉の裏には毛が密生している
ことがわかります。
毛のために葉裏は灰白色です。
ルーペで見たら星状毛が見えました。
5~7ミリの硬くて小さい実は、表面がこれまた星状毛に覆われており、
灰褐色でした。
軸との基部はこんなふうに五角形になっていました。↓
シナノキ科の植物です。
花は6月に咲くそうですが、是非見たいものです。
追伸:セイヨウボダイジュのことをリンデンバウムと言うそうです。
そういえば、ハーブティーで良い香りのする「リンデン」というのを
飲んだことがありました。
リンデンバウムで思い出すのは、確か中学校の音楽の時、歌わされた
シューベルトの「菩提樹」があります。
♪泉に沿いて 繁る菩提樹 慕いゆきては 美し(うまし)夢見つ
幹には彫(え)りぬ ゆかし言葉 うれし悲しに 訪いしその蔭
訪いしその蔭
この詩は、恋に破れた男の放浪の旅を描いた物語だったってこと、
最近知りました^^;;
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
オオスカシバの幼虫
- 2012年10月23日 16:43
- その他
こちらは朝から雨でした。夕方になり、やっと雨が上がったようです。
雨の中、水かさの増した川べりを散歩していたら、植栽されたクチナシの
木に異変が・・?
葉がほとんど丸坊主状態になっていました。
よく見ると、動くものを発見!
どうも蝶か蛾の幼虫のようです。
初めて見る幼虫なので家に連行し調べたところ(笑)、「オオスカシバ」
という蛾の幼虫で、スズメガの仲間でした。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
食卓の上の花瓶にクチナシの枝を挿し、しばし観察。
幼虫は体に白い線が通り、それに沿って小さな黒色の点々、
それとオレンジ(正確には両縁は白の点)の点々が9個あります。
お尻の方には1本の角のようなものが突き出ています。
幼虫の大きさは6センチ程です。
食欲旺盛で食べっぷりはなかなか・・、
するとほどなく数個の糞をたれたもう・・^^;
オシロイバナのような黒い種みたいな糞でした。
ちなみに糞の大きさは4~5ミリ程でした。
緑色のお顔↓
目などはわかりませんでした。
オレンジや黒の点々の様子や胴体や足の様子、少しはわかるかな^^。
オオスカシバの成虫は透かし羽(スカシバ)という名のとおり、
翅が透明な蛾で、黄緑の胴体は下の方が横縞になり、1本だけ赤茶の横縞が
目立つおしゃれな蛾です。
幼虫の食草はクチナシでした。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
トモエシオガマ
- 2012年10月18日 10:15
- 花
昨日から雨が降ったり止んだりで、すっきりしないお天気です。
きょうは、10日前に行った三河の山地の草地で見つけた
「トモエシオガマ」をお届けします。
この名前の由来について・・
①トモエ→花を上から見ると巴形をしているので・・。
参考→トモエソウ と同じ花の形。
②シオガマ↓
この花は花だけでなく、「葉まで美しい」ので・・
また一方、塩竃の浜は美しい...「浜で美しい」のは塩竃だ...
という語呂合わせで付いた名前、というわけだそうです^^;;
こんなのあり~~?と私も思いましたが・・(笑)。
シオガマギクの変種だそうです。
トモエシオガマ↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
紫紅色の花びらは唇形をしていて茎の上部にだけに付いていました。
そして、下の方の葉はこんなふうに付いていました。↓
花を上から見たところ↓
あららっ、巴に目がくらんでボケてしまい?(笑)・・すみません^^;;
気をとり直してアップで・・↓
今度は^^v・・確かに巴状です。
ゴマノハグサ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
シラネセンキュウ
- 2012年10月14日 15:07
- 花
秋祭りが各地で行なわれているかと思います。
近所の道路にも「祭礼中、通行止め」の立看がありました。
秋の一日、お祭りの声が聞こえるのもいいものですね~。
さて、先日行った、秋の低山地の湿り気のある林の縁に、
セリのような花が咲いていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
帰宅して調べたら、「シラネセンキュウ」でした。
「白根川芎」と書きます。
日光の白根山で発見され、薬用植物のセンキュウに似ているので、
名付けられたようです。
別名はスズカゼリ(鈴鹿芹)とも言われるそうです。
小さな流れの際にも咲いていました。
羽状に付いた柔らかい葉は互い違いに付いて、ひとつひとつの葉には
それぞれ不規則な深い切れ込みがありギザギザとなっています。
白色で小さな花の花びらは、普通は5枚だそうです。
(写真では6枚のも見えていますが・・^^;)
本州、四国、九州に分布します。
セリ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
マユタテアカネ
先日、里山に行った時に見たトンボのひとつ「マユタテアカネ」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
正面から・・↓
アップで・・↓
もう一度アップで・・↓
顔に眉のような黒い紋があるので、この名がついたそうです。
平地から丘陵地の、木陰があるような池や湿地などに見られるようです。
写真を撮った時もそばに池がありました。
面白い顔のアカトンボです^^。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
ハヤトウリ
- 2012年10月 8日 14:21
- その他
日差しはきついものの、秋の三連休をおくつろぎの方も多いことでしょう。
先回、掲載したビスカリア・ブルーエンジェルですが、2~3日前に見たら、
また復活して?元気に花をいっぱい付けていました^^;;
どうも私の一人合点のようだったのでお許しください。m(_ _)m
さて、昨日、里山に行く途中、道沿いにある八百屋さんに立ち寄りました。
生姜やいちじく、梨、トマトや小菊に混じり、初めて見る、
果物のようなものが目につき尋ねると、果物ではなく野菜とのこと・・。
なおも尋ねると、「ハヤトウリ」なるものとのこと・・。
実は見た目、洋ナシのような形をしています。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
大きさは縦11センチ、横8センチ(それぞれ最大値)で、
270グラムありました。
メキシコ南部から熱帯アメリカ原産で、わが国へは大正時代に鹿児島へ
導入されたのがきっかけで、薩摩隼人から「ハヤトウリ」(隼人瓜)と
呼ばれるようになったそうです。
別名「センナリウリ(千成瓜)」と言われ、沢山の実を付けるそうです。
ゴーヤみたいに細い茎、つるにひとつずつ実がぶら下がっているようです。
漬物やサラダ、炒め物、煮物にするそうです。
さあ、お料理しようと、縦半分に切ってみました。↓
真ん中に柔らかい白い種がひとつありました。
ネットで調べたら、種で増やすのではなく、実ごとそのまま植えて
栽培するようです。
ちょっと変わっていますね。
瓜の皮を剥いて薄切りにして生のまま口に運ぶと、あらっ?、不思議!
シャキシャキしているのですが、結構甘くてしかもジューシーでした。
初めて食べたのですが、結構、いろいろいけるかも?!
色々悩んだあげく、結局シンプルに昆布とかつお節で薄味に煮ました^^;。
冬瓜よりシャキシャキ感があり、自然の甘さは少し強めでした。
もうひとつ残っていますが、今度は違う調理法で食べてみたいと思います^^。
ウリ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ビスカリア・ブルーエンジェル
- 2012年10月 2日 21:19
- 花
今年8月初め頃、川原にブルーの花がいっぱい咲いているのに
気がつきました。
たまたま役所の人が通りかかったので尋ねたら、役所が植えたのでは
ないとのお答え・・、上流から何かの加減で流れてきてそこに根付いて
増えたのかしら?それか誰かが植えたのか?わかりません。
それから時々気になって見ていたのですが、一週間前までは
咲いていました。
そして、きょう、一週間ぶりに川沿いを散歩したら、さすがにもう、
花はほとんど終わっていました。
というわけで、このブルーの花、「ビスカリア・ブルーエンジェル」を
お届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
対岸のビスカリア・ブルーエンジェルです。↓
こちら岸のビスカリア・ブルーエンジェルです。↓
ナデシコ科の植物です。
<お詫びと訂正>
2017年9月、匿名さまより間違いをご指摘いただきました。
この写真の花は「ビスカリア・ブルーエンジェル」ではなく、
キツネノマゴ科ルエリア属の「ヤナギバルイラソウ」です。
大変、申し訳ございませんでした。
「ヤナギバルイラソウ」の正しい記事はこちら→ヤナギバルイラソウ
- Comments: 4
- TrackBacks: 0






































 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

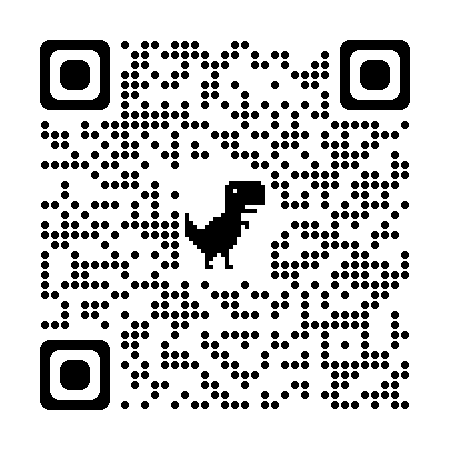 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







