Home > Archives > 2012年6月 Archive
2012年6月 Archive
フタリシズカの実
きょうで6月ももう終わり。
今月は皆様のおかげで1年7ヶ月ぶりに2桁回数アップできました。
有難うございますm(_ _)m。
さて、きのうの16時半頃、今季初めてマンションで
コシアキトンボが旋回しているのを見ました。
例年より遅めのお出ましか~^^。
いつもより2メートル程上空を旋回していました。
きょうは滋賀の山でであった「フタリシズカ」を
お届けします。
「二人静」と書きます。
(余談:「二人静」といえば、両口屋ですが、こちらは
「ににんしずか」と呼ぶ和三盆のお菓子です^^;)
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
「フタリシズカ」という名は、静御前とその亡霊の舞姿を
2本の軸にたとえ、名付けられたようです。
花穂が2本、だから「一人静」に対して「二人静」と
私も思っていましたが、実際には穂が1本、2本、3本、4本・・数本と、
まちまちで一定しないそうです。
山野の林下に生え、草丈は30~60センチ程です。
群生しているのもありました。
茎の先に穂状に米粒のような花を付けますが、もう花が終わって
緑の実が付いているようです。
センリョウ科の植物です。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
ニリンソウ
- 2012年6月27日 21:11
- 花
ここ数日前から市街で植栽されたハマユウの白い花をよく見ます。
この季節、白色や青系の花が爽やかですね^^。
きょうは滋賀の山に咲く植物に戻ります^^;
滋賀の山に行ったのはかれこれひと月前、時々脱線するので(笑)、
そして、まだ調べがついていない植物もあり掲載がままなりません^^;
まことに遅れ、あいすみませんが、ご用とお急ぎでない方は、
もう少しおつきあい下さいませm(_ _)m。
さて、林の縁にポツポツと咲いてた「ニリンソウ」をお届けします。
ニリンソウといえば"ふたり~は二輪草~♪"というあの歌が
ありましたね^^。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
上から撮った写真です。
花の大きさは2センチ程です。ちょうど1円玉の大きさです^^。
ニリンソウといいますが、茎の先に1個、もしくは2個の花を
付けていました。
下の写真のは、1本は花がとれていましたが・・。
図鑑によると、4個まで花を付けることがあるそうです。
また、葉は3枚が輪生し、柄がなく、それぞれが深く切れ込んでいます。
そして、葉に、しばしば小さな班が入ります。
花びらに見えるのはガク片だそうで、5枚、もしくは6枚のがありました。
6枚のもの↓
図鑑によるとガク片が7枚のものもあるそうです。
白色のが多いですが、ピンク色がかったものもありました。
雌しべは多数ありましたが、実は数個しかできないようです。
北海道~九州に分布します。
キンポウゲ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ロウムシ
- 2012年6月24日 13:34
- その他
今年はゴーヤの苗を植えるのが遅かったので、今朝、今季初めての
ゴーヤの花が2つ咲きました。
ふと、レモンの木を見たら、葉に白い綿?のようなものが見えました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
何?と思って触ってみると、綿ではなくて硬いものでした。
連れ合いに聞くと、ロウムシじゃないか?とのこと・・。
ロウムシ?初めて聞く名です。
早速、ググッてみました。
そうしたら、ロウムシはカイガラムシの一種でした。
カイガラムシといっても大きさや形などは様々とのことで、
名前が付いている種類だけでも400種以上おり、実際はその倍くらい
存在するらしいです。
アップにしてみました↓
お椀のように丸く盛り上がったのがロウムシ類のようです。
柑橘類に付くロウムシ類にはルビーロウムシ、ツノロウムシ、
カメノコロウムシの3種があるそうです。
ルビーロウムシ、ツノロウムシはいずれも蝋質物が成虫で4~5ミリ程と
あったので、これは成虫で蝋質物が9~10ミリ程の大きさがあるので、
ツノロウムシかな?
葉から外してみたら、こんなふうでした。↓
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
アジサイ その4
- 2012年6月22日 18:02
- 花
半田の某有名和菓子店の生菓子に「四葩の花」と書いてありました。
さて、「四葩」は何と読むのでしょう?
正解は「よひら」。
「葩」とは一字では「ハ」と読み、「はな」という意味だそうです。
では「四葩」とは何か?
四つの花?
四つの花びら(ではなくて、じつはガク)が目立つので、
「四葩」は「アジサイ」の別名だそうです。
(本当の花は真ん中にある小さな点のような部分です。)
御用とお急ぎでない方は、ここで紫陽花を見て、しばしひと休み
なさって下さい。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
・・・
・・・
・・・
・・・
生菓子はこちら→ 「四葩の花」
- Comments: 6
- TrackBacks: 0
コクサギ
2~3日前に実家に行った時、垣根に深い赤ワイン色の
クレマチスが咲いていました。
どうもグレイブタイ・ビューティーという名のようです。
花瓶に挿して、つかの間楽しみました。
きょうは滋賀の山の沢沿いにあった「コクサギ」をお届けします。
「小臭木」と書きます。
文字通り「小さな臭い木」という意味で、葉を揉むと独特の臭気が
あります。
そして、一番の特徴は葉の配列にあります。
一見、単純に互い違いに葉が付いているように見えますが、
よく見ると、2枚づつ互い違いになっている所があります。↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉は柔らかく、長さ5~13センチ程で表面は光沢がありました。
コクサギは雌雄異株です。
写真を撮った木は雌株のようで実が生っていました。
実は1~4つに分かれています。↓
ミカン科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ウンモンスズメ
- 2012年6月19日 11:46
- その他
今朝、ゴミ出しの帰り、何やら蛾を発見!
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
全身が翡翠色っぽく、雲紋模様も美しい~♪
マンションのエビネの葉に止まっていました。
葉陰で休んでいるのかな?
お休みのところすみませんが、横からも一枚お願いします^^;
早速調べたところ、スズメガの一種の
「ウンモンスズメ」のようです。
大きさ(開張)は7センチ程でした。
幼虫は、ケヤキなどの葉を食べるそうです。
マンションにはケヤキが何本もあるので然り。
北海道、本州、四国、九州 に分布するそうです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
タニギキョウ
- 2012年6月18日 18:11
- 花
時々通る道に数日前まで白いサンゴジュの花が咲いていましたが、
色が変わり、ほとんど道路に落ちてしまいました。
実家の庭のクチナシの白い花は、まだ咲いています。
きょうは滋賀の山の谷筋に生えていた「タニギキョウ」を
お届けします。
「谷桔梗」と書きます。
谷に生える桔梗という意味ですが、とても小さくて可愛い花でした。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉には柔らかい短毛があり、縁に粗いギザギザが数個あります。
大きさ5~8ミリで、先が5つに深く裂けた白色~淡紫色を帯びた花を
上向きに付けます。
北海道、本州、四国、九州に分布します。
キキョウ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
コンロンソウ
- 2012年6月17日 13:37
- 花
最近、ツバメが飛ぶ姿をよく見かけます。
すっかり梅雨空です。
さて、きょうも滋賀の山にあった植物の中から・・、
沢沿いにあった「コンロンソウ」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
「崑崙草」と書きます。
この花が咲いている様子を、中国の崑崙山に降り積もった白い雪に
見立てて名付けられました。
葉は長さ3~7センチほど、先が尖り、縁にはギザギザがあります。
この写真ではいくつか花が散ってしまったようですが、残った白い花を
見ていただくと、アブラナ科の特徴である十字花(4枚の花びら)です。
雄しべは6本、雌しべは1本です。
北海道、本州、四国、九州に分布します。
アブラナ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
エビネ その2
- 2012年6月14日 13:59
- 花
昨日、マンションの庭のケヤキの上で何やらギィーという声が・・
上を仰ぐと、コゲラがケヤキの樹皮を嘴で剥いでポイッと捨てている
ではありませんか。
ほどなく、もう一羽コゲラが現れ、これまたギィーとご挨拶。
夏にもコゲラは姿を見せてくれました(*^^)。
さて、マンションの木陰にはエビネが毎年花を咲かせてくれます。
今年は少し増えたようですが、咲いたのは5株ほどでした。
そのエビネは、5月中旬にはもう咲き終えてしまいましたが、
滋賀の山のエビネは5月下旬に咲いていました。
遅くなりましたが、きょうは滋賀の「エビネ」をお届けします。
下山途中の疎林の中で一株だけ咲いていたのを見つけました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
「海老根」と書きます。
地下茎がエビのように見えるところから名付けられました。
エビネは野生蘭の代表的なものですね。
このエビネの高さは20センチ程でした。
何か虫が訪れていました。何虫かな?
味わいのある花で人気もあり、展示会ではよくエビネを見ますが、
こうして山で見る自生のエビネは格別です。
*マンションのエビネ→過去記事エビネ
よりアップで・・↓
見られたことに感謝(^人^)です。
日本原産です。
ラン科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
チドリノキ
- 2012年6月12日 20:30
- 木
雨が降ったり止んだりの一日でしたが、午後から散歩に出かけたら、
いつもの川に黄色の長靴を履いた(笑)コサギが来ていました(^^)。
きょうも滋賀の石灰岩の山にあった植物をお届けします。
動物の名の付いた植物です。
残念ながらコサギではなく、チドリです。(笑)
「チドリノキ」です。
「千鳥の木」と書きます。
実の翼の様子を千鳥が群れ飛ぶ様子に例え、名付けられたそうです。
沢沿いの湿った所に生えていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
少し薄い手触りの葉は、10~15センチ程の長さがあり、
向き合って付いていました。
葉にははっきりとした主脈と側脈があり、側脈は平行です。
葉裏の主脈沿いには毛が密生していました。
そして葉のアップの写真がなくて申し訳ありませんが、葉の縁は
重鋸歯(ギザギザの中にまたギザギザがある)になっていました。
雌雄異株です。
本州、四国、九州に分布します。
(意外にも)カエデ科の植物です(^^;)
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
カナクギノキ
- 2012年6月11日 21:14
- 木
数年前の秋に六甲山に行った時、黄葉したカナクギノキを
見たことがありますが、写真が残っていません(涙)。
落ち着きのある黄色だった印象です。
先月下旬に滋賀県の山で、またカナクギノキに出合いました。
きょうはその「カナクギノキ」をお届けしたいと思います。
「鉄釘の木」と書きます。
カナクギとは、釘(くぎ)のことではなく、樹皮に見られる
「鹿の子模様」から「かのこぎ」といわれていたのが訛った
という説が有力だそうです。
高さ6~15メートル程の落葉高木で、雌雄異株です。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
樹皮は淡褐色。
幹は太くなると小さな皮目が目立つようになり、
老木では不規則に剥がれます。
葉は長さ6~13センチ程で、幅は1.5~2.5センチ程で細長い。
葉の表面は緑色で、裏は白っぽい。
花は葉が出ると同時に開花するそうです。
カナクギノキの花 (多分、雄花)が落ちていました。
見上げると、花がいっぱい付いていました。
本州(箱根以西)、四国、九州の丘陵帯の林に生えます。
クスノキ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
クロタキカズラ
- 2012年6月 7日 10:12
- 木
時々通る道のアメリカキササゲの花はほとんど終わり、
サンゴジュにいっぱい花が付いていました。
そして、白いキョウチクトウも咲いていました。
さて、きょうは、先月下旬に滋賀県の石灰岩質の山に行った時に
出合った「クロタキカズラ」をお届けします。
「黒滝葛」と書きます。
名の由来は高知県黒滝山で初めて見つけられたことによります。
山の林のカナクギノキに巻きついていました。↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
少し歩くと、今度はミズナラの木に巻きついていました。↓
山地の林内のやや湿った所に、まれに見られる落葉性のつる植物です。
雌雄異株だそうです。
葉は互い違いに付いて、先は尾状に尖っています。
縁には不揃いの粗いギザギザがあり、ギザギザの先は禾状に
鋭く尖っています。
また、葉の裏は緑白色で、葉の両面には短毛が生えています。
本州(近畿地方以西)、四国、九州に分布します。
クロタキカズラ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
オヒョウの実
- 2012年6月 5日 21:00
- 木の実
今朝、レモンの花が6個も花開き、ベランダは甘酸っぱい香りに
包まれました^^。
ピンク色が可愛いザ・フェアリーも咲いてきました。
朝からいい気分でした^^。
さて、きょうは「オヒョウの実」をお届けします。
オヒョウは北海道のアイヌ語で、樹皮でアイヌの人の着物(アッシ)を
作ることに由来するそうです。
なので、アッシ、またはオヒョウニレという別名があります。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
オヒョウは高さ25メートルにもなる落葉高木ですが、写真のは
若いオヒョウだったので高さは3~4メートルでした。
花はもう終わったようで、実が付いていました。
オヒョウの実は6月頃に褐色に熟し、長さは1.5~2センチ程で、
円形から広い楕円形で扁平です。翼果というそうです。
葉先がフォークのように切れ込む葉は特徴的です。
先が尾状の葉の他、この写真の葉のように3~5裂するものが
混じっています。
図鑑によると9裂のものもあるそうです。
また、葉は縁に重鋸歯(2重のギザギザ)があり、互い違いに付きます。
葉の両面には毛が生えており、触るとザラザラします。
北海道、本州、四国、九州に分布し、山地に生えます。
ニレ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
サツキヒナノウスツボ
- 2012年6月 1日 14:55
- 花
時々通る道にある、アメリカキササゲの花が
せわしく落花していました。
きょうから6月ですね。
きょうは滋賀の山で出合った「サツキヒナノウスツボ 」をお届けします。
登山途中の道脇のやや日陰の湿った林で、トリカブトの
群生の中に、これを見つけました。
草丈は60センチ程でしたが、後ろへ下がることができず、
草体全体が撮れませんでした(泣)
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉は向き合って付いており縁にギザギザがあります。
茎には毛が多いです。
そうそう、「五月雛の臼壺」と書きます。
五月に咲く花の形から名付けられたそうです。
花色は暗紫色で地味ですが、花の形はなかなかユニークです。
風でブレてしまって見にくいですが、白っぽい雄しべと雌しべ
(雄しべの下の細い棒)が飛び出てるのがわかりますか。
もう、一枚!
ゴマノハグサ科の植物です。
お知らせ:
開花期と分布地域から考えて「サツキヒナノウスツボ」と訂正させて
いただきます。
開花期は5月頃。
分布地域は秩父・奥多摩の山地、中央アルプスの伊那側、伊吹山地(6/3fab)
- Comments: 2
- TrackBacks: 0

















































 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

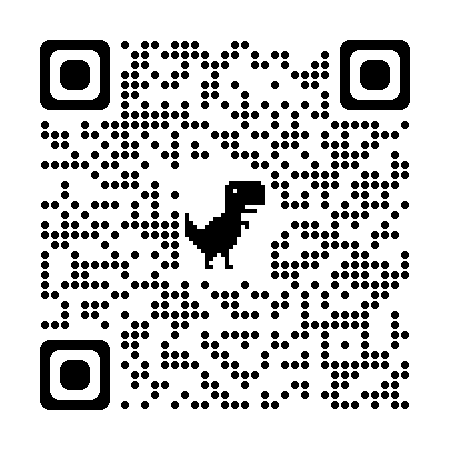 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







