Home > Archives > 2011年8月 Archive
2011年8月 Archive
ケカモノハシ
- 2011年8月30日 20:27
- 草
こちらは昼間とても暑かったです。ふ~(^_^;;)。
おかげで蚊も出て、蚊取り線香が大活躍。
まだまだ蚊取り線香は手放せません(*_+ )
また、きのう、早朝の空にコウモリの姿を見ました。
夜、コウモリが飛んでいるのを見たことは何度かあるのですが、
明け方見たのは初めてです。巣へ帰る前だったのかな・・。
さて、きょうは海浜の植物を紹介します。
海の砂地の植物にしては珍しく、背丈が高めの植物が一叢
生えていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
ケカモノハシでした。
「毛鴨嘴」と書きます。
花穂をアップ↓
花穂は1本に見えますが、その花穂を横にずらすと、あら、不思議!
このように2本に割れてしまいました。↓
指入り写真でごめんなさい^^;
それが鴨のくちばしに見えることから、カモノハシと名付けられました。
そして、毛が花穂はじめ葉や茎にも生えているので、ケカモノハシと
名付けられました。
この毛が潮風や乾燥から身を守っているのかな。
北海道から九州の海岸砂地に生えています。
イネ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
モノサシトンボ
まだ残暑もありますが、もうすぐ夏も終わりですね。
セミが鳴いていますが、その声も一時期に比べると、
少し勢いがなくなりました。
先月、玄関にあるスパティフィラムに水をやろうとしたら、
いきなり、小さなトンボがふわりと先に止まりました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
モノサシトンボです。
去年も玄関で姿を見ましたが、今年もまた来てくれました。
来年もまた顔を見せてね・・。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
コマツヨイグサ
- 2011年8月21日 16:03
- 花
こちらは雨や雷のためか急に涼しくなりましたが、今は
クマゼミやアブラゼミが鳴いて、ちょっと蒸し暑いです。
皆様の方はいかがでしょうか?
きょうは夕暮れ間近な浜辺に咲いていた「コマツヨイグサ」
をお届けします。
「小待宵草」と書き、小型のマツヨイグサという意味です。
同じ仲間のマツヨイグサやオオマツヨイグサも、どれも帰化植物で、
日本に江戸~明治時代に渡来し、野生化して繁殖しています。
花の形や咲き方もよく似ています。
(写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
が、茎が這う点が最大の特徴です。
その他、花が小さく、葉に変化が多くギザギザや羽状まであります。
また、生える場所は海岸か海岸に近い草地に限られ、
内陸で見ることはないそうです。
花期は5~11月 です。
本州、四国、九州、沖縄に分布する帰化植物です。
ハート形4枚の花びらを持つ花は径2~3センチ程と小さく、
しぼんだ花はやや赤味を帯びていました。
雌しべの先は4つに分かれているようで、雄しべは8本です。
そして、茎や葉に毛が多いです。
アカバナ科の植物です。
- Comments: 8
- TrackBacks: 0
アオスジアゲハ その4
初盆も無事済んで、ちょっと一息。
アオスジアゲハの続きをお届けします^^;
帰宅して見に行くと、もう、こんなふうに・・?!
緑の蛹に変身していました~☆彡
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
上から見ると、葉の裏にこんなふうにね↓
すご~い!まるで葉脈そっくり~♪
蛹は葉を食べる必要がないので、木の外側から見えにくい葉裏に、
鳥などの外敵に見つからないように隠れているのです。
7/28
まだ、緑の蛹のまま・・。
8/3の様子↓
まだ、ずーっと緑の蛹のまま・・。
大丈夫かな?
その後毎日見ていても変化がなかったのですが、ついに8/8の朝、
8時ちょっと前に羽化していたというわけです^^;
羽化したばかりの記事はこちら→ アオスジアゲハ その2
そうそう、後日、アオスジアゲハの幼虫がまた葉に付いているのを
見つけ、初期の幼虫の写真が撮れました。
また後先になってしまってすみませんが、おまけに載せますね^^;
↑体の回りに面白い形の毛が生えています。
↑頭でっかちで緑色です。
↑体の色が明るくなり、角?のようなものが6本見えます。
追伸:きょう、アクセス数が20万回を超えたようです。
これも皆様のおかげと感謝しております。
これからも応援よろしくお願いしますm(_ _)m。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
アオスジアゲハ その3
そもそもアオスジアゲハの観察を行うきっかけは、
ベランダにひとり生えしたクスノキの葉に、何か虫に
食べられたような形跡があったので、注意して見ると、
青虫と葉裏にサナギの殻が三つ見つかったことが発端でした。
調べたらどうもアオスジアゲハの幼虫と蛹の殻でした。
7/26↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
終齢幼虫↑
クスノキの葉は表と裏では色が違うので、幼虫が
葉裏に行くととても目立ってしまいます。
ふだん、幼虫は葉の表にいて葉の表側の色と同じ色をして、
外敵から目だたないようにしています。
蛹の殻↓
青虫は葉裏にくっつき、じっとして動きませんでした。
が、少しして糸を出し、体つきも変わっていました。
7/27↓
上から見ると↓
目のような模様があります。本当の目は、隠れて写っていません。
横から見ると↓
口に見える所に球のようなものが見えますね。
球が葉と接する所に黒いのがチラッと見えませんか?
これが本当の目だそうです。
どうも蛹になる前の脱皮中だったようです。
が、途中で所用が入り、その後は見ることができませんでした~(泣)。
そして次に見た時は・・?!
次回へ続く・・^^。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
アオスジアゲハ その2
立秋過ぎたのに猛暑が戻り、たまりませんね_(・_.)/ コケッ。
皆様、残暑お見舞い申し上げます。
さて、きのうの朝8時頃、なんと羽化してまもないアオスジアゲハが、
サッシの縁につかまっているではありませんか?!
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
室外機との狭間だったので、ベランダのキンカンの葉にでも止まらせ
ようとしたら、いきなりベランダの外へはばたいて、カイヅカイブキの
葉にちょっとぶらさがり一服。
それからすぐに空の彼方に飛んでいきました。
あ~っ、よかった!
羽化した瞬間が見られなかったのは残念だったけど、無事に蝶になり、
大空へ飛んでいく姿を見られたのはうれしかった~♪
じつはちょっと前からアオスジアゲハを観察していました(*^^)v
緑の蛹になってから、ちょうど12日めの羽化でした。
次回からアオスジアゲハの観察をお届けしたいと思います。
青虫なども出てくるので、お嫌いな方はスルーしてくださいねm(_ _)m。
過去記事はこちら→アオスジアゲハ
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ハマゴウ
- 2011年8月 4日 16:35
- 花
先日、急に思い立って海に行きました。
午後6時頃、海岸の砂浜に青紫色の花がいっぱい咲いていました。
わぁ~、まるで、青い絨毯が敷きつめられたかのよう・・。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
帰宅して調べたら、「ハマゴウ」でした。
海浜植物にはハマのつく名前のものが多いですね。
「浜栲」と書きます。
砂浜に生育する海浜植物なので、種が海流に乗って運ばれ、
本州、四国、九州、沖縄から中国、朝鮮、東南アジア、ポリネシア、
オーストラリア等、広く分布しているそうです。
波打ち際よりは少し高台の方に群生していましたが、だんだん
低い方へも、砂に埋もれながらも茎を伸ばし這っています。
一見、草のようですが、草ではなく、低木だそうです。
浜へ枝を伸ばすハマゴウ↓
葉の表は緑ですが、裏面には灰白色の毛が密生しており、
白っぽく見えます。
花は漏斗状で唇形をしており、合弁花です。
上唇は2裂し下唇は3裂しており、雄しべは4本、
雌しべの先は2裂しています。
そして、雄しべも雌しべも花の外へ突き出ています。
花の一部には白い毛が生えています。↓
実ができているのもありました。
実はガクに包まれています。
クマツヅラ科の植物です。
おまけ:
ここは中部国際空港(セントレア)が近いので、飛行機が
低空で飛んでいます。
浜辺にはハマゴウの他、帰化植物のコマツヨイグサも生えていました。
午後7時を過ぎてやっと日が落ち、だんだん暗くなり始めると、
コマツヨイグサが文字通り宵の中で、しだいにあちこちで、
開花し始めていました。
昨今、海浜植物の生息範囲はどんどん狭まっていると聞きます。
子供の頃、海水浴を楽しんだ砂浜はそのうちなくなってしまい、
それに伴い、海浜植物も・・・。
そうならないように、子子孫孫、この景色を守り伝えたいものです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0































 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

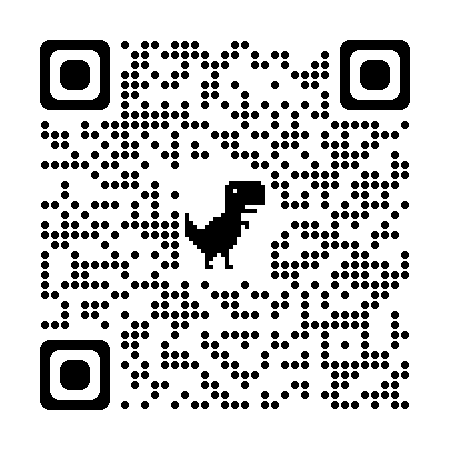 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







