Home > Archives > 2010年11月 Archive
2010年11月 Archive
東山植物園の紅葉
- 2010年11月30日 22:19
- その他
皆様、こんばんは。
きょうで11月も終わりですね。
今や紅葉も真っ盛りで、こちらでは香嵐渓が有名ですが、
なかなか時間もとれず、先日、手近な東山植物園に行ってきました。
しばし、ごいっしょくだされば幸いです。
まずは植物園への道すがら・・↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
空を仰いで~、\(^▽^)/わ~い♪↓
さて、植物園の中へ・・
こちらの場所は、植物園の紅葉鑑賞の
一押しスポットだとか・・↓
奥池にやってきました・・↓
もう一枚・・↓
そして、山の方に上がって・・↓
東山の紅葉もなかなかに捨てがたい~(★^ー゚)bネッ♪
おかげでいい息抜きができました(^人^)
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
カイノキ
- 2010年11月24日 05:28
- 木
きのうの朝、マンションの歩道は一面、錦の絨毯に
彩られました\(^-^)/。
残念ながら、時間に追われ写真は撮れず・・(泣)
きょうは替わりにちょっと前に撮ったカイノキをお届けします。
「楷樹」と書きます。
カイノキは、直角に枝分かれすることや小葉が綺麗に揃っている
ことから、楷書にちなんで名付けられました。
中国、台湾原産の落葉高木で、中国名を楷と言うそうです。
別名のクシノキ(孔子の木)は中国の孔子廟に植栽され、科挙に
合格した者に楷の笏を送ったことから、学問の聖木とされました。
日本には大正時代に渡来したそうです。
岡山県の閑谷学校の楷の木が有名ですね。
ちょうど今頃は赤と黄の2本のカイノキが見事に紅葉している
ことでしょう。
閑谷学校のカイノキの落葉は受験のお守りとして持ち帰られるそうです。
さて、今回、私が撮ったのは植物園のカイノキです。
見上げたところ、高さは10メートル程でした。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
樹皮はこんなふうです↓
葉はこんなふうです↓
秋に美しく紅葉した姿です↓
アップで・・。
来月になると多分こんなふうになる予定・・^^;↓
(一昨年の12月に撮った写真です)
ウルシ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ナラメイガフシ
- 2010年11月20日 16:43
- その他
山道を歩いていたら、4センチ程の大きさの実?がいきなり
目に入りました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
てっきりクリのイガかと思ったのですが、なんだかちょっと変?
なので帰宅して調べました。
そしたら、「ナラメイガフシ」という虫こぶでした。
「楢芽毬五倍子」と書き、"ナラ""メ""イガ""フシ"です^^。
ナラ科の若い木の芽を好んで産卵し、イガ状のフシを作るので、
こう名付けられました。
上から撮ったところ↓
実ではなくて、虫の子のお家なんですね^^;
ナライガタマバチがコナラに産卵し、その幼虫が寄生して出来たもの
だそうです。
最初は緑色で、後に枯れて褐色になるようです。
コナラ、ナラガシワ、ミズナラ、カシワの若葉の芽にできるそうです。
北海道~九州に分布するようです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
イスノキの虫こぶ
- 2010年11月17日 21:28
- 木
だんだん寒くなり、あちこちの紅葉も見頃になってきましたね。
マンションのサクラの赤、ケヤキの黄、満更でもありません^^。
さて、きょうはサクラやケヤキの落葉樹ではなく、常緑樹ですが、
変わった名前の木を紹介します。
「イスノキ」です。
えっ?いすって椅子のこと~?
私もそう思ったひとりで~す(^^;)
残念ながら、違いますっ_(・_.)/ コケッ。
なんと「蚊母樹」あるいは「柞」と書くそうです。
語源はこちらをご覧ください→イスノキ
高さ20メートル程になる常緑高木だそうです。
この木はせいぜい数メートルでしたが・・。
樹皮はこんなふうでした↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
楕円形で厚みがあり、光沢がある葉が互い違いに付いていました↓
葉に虫こぶが付いていました↓
葉の面に小型の黒茶色のホクロのように隆起したものがいくつかと、
大きく肥大して何かの実のような形をしたものが付いていました。
やや白っぽい葉裏にも隠れるように虫こぶが付いていました↓
帰宅して「虫こぶハンドブック」で調べたところ・・
大型の虫こぶは判明いたしました。
でも小型のほうは決め手を欠くので今回はスルーします^^;
大型のものは、モンゼンイスアブラムシが作ったもので、
「イスノキエダチャイロオオタマフシ」のようです↓
大きいものは8センチ程にもなるようです。
これは6センチ程でした。
成熟すると木質化して硬くなり、内部が空洞となり、
笛として使えるようです。
残念ながら穴の写真を撮りそこねましたが、穴に唇を当てて吹くと
ひょうひょうと音が鳴るので、ヒョンノキとも言われるそうです。
このように「虫こぶといえばイスノキ」といわれるほど、
イスノキの虫こぶは有名だそうです。
本州、九州、屋久島に分布します。
マンサク科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
東山秋風景
- 2010年11月14日 17:55
- その他
朝から曇り空ながら、この週末は秋の行楽シーズンで、
お出かけされた方も多いことでしょう。
私は、土曜は半日がかりでベゴニアを部屋に入れ、きょうは
マンションの花壇にチューリップ等の球根を植えました。ふ~(^_^;;)
さて、きょうはいつもと違って、先週末に行った東山公園の風景を
ほんの少しですが、お届けしま~す♪
動物園から見た東山スカイタワー、
左にモノレールも見えていますね。↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
アシカの池。↓
上池(ボート池)。
人出があって、ボートがたくさん出動し、
家族の楽しそうな会話も聞こえてきました。↓
植物園のカイノキも紅葉していました。
この頃、午後3時過ぎていました。↓
秋の日は釣瓶落としとは、言い得て妙ですね・・。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
センブリ
- 2010年11月12日 21:41
- 花
実家にあるカリンが今年は当たり年で、いっぱい実が生りました~♪
半分以上は残念ながら地面に落ちてしまいましたが、
まだ残っているのは見事な黄色に色づいてきました。
午後、友達と朗読劇を観に行きました。
演目は泉鏡花の「天守物語」でした。
なかなかに好演でした。
さて、きょうは「センブリ」をお届けします。
「千振」と書きます。
「千回振出してもまだ苦い」ということから名付けられました。
花、葉、茎、根はすべて苦く、全草を薬用に用いるそうです。
日本の民間薬の代表で、生薬名は当薬(とうやく)と言います。
当薬とは「当(まさ)に薬(くすり)」の意味だそうです。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
高さは20センチ程でした。
茎の断面は四角く細長い線形の葉が向かい合って付いています。
直径2センチ程の花は合弁花で、深く5裂しています。
花は白色で縦に紫色の筋があります。
雌しべは1本で、雄しべは5本、花の真ん中にはモジャモジャの
白い毛が生えています。
北海道~九州の山地の日当たりのよい草原に分布します。
リンドウ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ムラサキセンブリ
- 2010年11月 9日 12:27
- 花
きょうは、風が強く落ち葉を掃いても処置なし、
適当に掃いておきました・・(^m^;
ハンギングしてあるベランダのデンドロに水をやろうとしたら、
巻いてある水苔の中からいきなりヤモリがご挨拶~♪
うちは玄関やらお風呂場、天井、そしてベランダ・・そうそう、
先日は室外機の中にヤモリがいて漏電騒ぎもあったのですが・・
とにかく守宮に守られているようです☆\(^^;
きょうも2週間程前に撮った写真のひとつ、
「ムラサキセンブリ」をお届けします。
「紫千振」と書きます。
紫色のセンブリということで名付けられました。
センブリについては、また、後日・・。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
花はひとつしか開いていませんでした。
高さは50~60センチでした。
葉は細く、長さ2~4センチ程で向かい合って付いています。
茎はこんなふうに暗紫色を帯び、四角張っています。
直径3センチ程の花は深く5裂し、一見、合弁花とは思えません。
淡紫色で濃い紫色の筋があります。
雌しべは1本で先が二つに割れ、雄しべは5本、花の真ん中には
モジャモジャの白い毛が生えていますね。
センブリよりも背丈があり、花もやや大きめです。
2週間程前は、ほとんどこのように蕾が多かったですが、
今頃は満開で賑やかなことでしょう。
関東以西の本州~九州の、日当たりの良い蛇紋岩地帯や草原に
分布します。
リンドウ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ナンテンハギ
- 2010年11月 8日 12:39
- 花
朝、晴れてたのに、今にも降り出しそうなお天気になってしまいました。
先日、コーヒー豆を買いに行ったら、その店のオリーブの木に実が
付いていました。
ご店主にたずねたら、7年越しで実が付いたとのこと・・。
今はオリーブの実の生る時期なんですね・・
そろそろワインが飲みたくなる季節でもありますね^^。
さて、きょうは2週間程前に撮った「ナンテンハギ」をお届けします。
「南天萩」と書きます。
葉がナンテンに、花がハギに似ているので名付けられました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉が2枚ずつ付いているので、フタバハギともいうそうです。
青紫色の蝶形の花を多数つけます。
もう、実が付いているものも見られました。
実は2~3センチ程で、ソラマメを小さくしたような形です。
実際、ソラマメの仲間でした^^。
春先に伸びる若芽は山菜として食べることができ、茹でると小豆の
ような匂いがするのでアズキナともいうそうです。
北海道~九州の日当たりのよい山の土手や草地に分布します。
マメ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
松虫考
- 2010年11月 4日 10:59
- その他
とってもいいお天気で~す。
皆さん、いかがお過ごしですか~\(^o^)/
さて、先日アップしたマツムシソウの名の由来云々ですが、
遅くなりましたが調べたことをご報告しますね(^^;)
>花が咲き終わったあとに残る坊主頭のような形が
松虫鉦(まつむしかね)とよばれる仏具の形に似ているから・・
とのことで、松虫鉦を調べましたが、どうやら仏具ではなく楽器で、
歌舞伎の音響効果に使われる鉦のことらしいです。
鉦とは諺(ことわざ)にある「鉦や太鼓をたたいて探す」の鉦です。
さて、松虫鉦の"松虫"とは、 木の板に伏せ鉦を二つ並べたもので、
撞木(しゅもく)→鉦をたたく道具、木魚をたたくバチ?を小さくした
ような形のもの・・でチャリンチャリンと打って音を出す。
高く、軽い感じの音で松虫の擬音のような音がするそうです。
あ、鉦とは金属製の当り鉦をより小さくしたものです。
紐がついていない代わりに足が3つ付いていて、
台に置いて打つとのこと。
サイズの違うものを複数使用することもあるそうです。
こちらをご覧ください→ 松虫
ネットでいろいろ調べたのですが、かなりハマリ、ただでさえ、
おぼつかない頭がよけい混乱をきたしましたヨロヨロ~~~_(・_.)/
強いて私見をまとめれば、以下のとおりです。
その前にブレイク・タイム!
ちょっと一輪、マツムシソウ~♪
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
歌舞伎の松虫鉦の音がマツムシの鳴き声に似ていて、
その松虫鉦の形がマツムシソウの花の形に似ていたので、
マツムシソウになったのかな。
マツムシソウが咲いたときの花の形は婦人用の帽子の形にも見え、
伏せた鉦の形にも見えませんか?(^^;)
一度、歌舞伎の松虫鉦の音色を聞いてみたいものです。
どんな演目の時、使われるのかな?
その他、その昔、マツムシはスズムシだったetc.・・調べていくと
よけいハマリそうなので、先を急ぐ身としては・・(いずこへ?
ご期待どおり突込みますヘ(__ヘ)☆\(^^;ナンデヤネン
このへんでマツムシ考はお開きにさせていただきます_(・_.)/ コケッ。
*末筆ながら・・
私のつたないど~でもいい話に興味を持って、松虫鉦について
調べていただいた方には、この場を借りて御礼申し上げます。
また、違うご意見がありましたらお知らせくださいねm(_ _)m
おまけ:
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
エンシュウハグマ
- 2010年11月 2日 23:04
- 花
街路樹のナンキンハゼが色づいてきました。
霜月の声を聴き、日ごと山から里へと紅葉も下りつつあるようです。
きょうは「エンシュウハグマ」をお届けします。
「遠州白熊」と書きます。
遠州(静岡)に分布するので"エンシュウ"、チベットのヤクの尾の毛
で作られた"ハグマ(白熊)"に似ていることから名付けられました。
写真は、東三河の蛇紋岩の山の林内で咲いていた「エンシュウハグマ」
です↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
上の写真の花は満開でした。
高さは20センチ程でした。
葉は掌状に3~5裂し、葉が深く切れ込むのが大きな特徴のひとつです。
縁にギザギザがあります。
葉のアップ↓
花は上から下へと咲いていくようです。
蕾はこちら↓
花は3つの小さな花が集まって、ひとつの花となっているようです。
花びらは5つに深く裂け、うっすらとピンクがかった先がくるんと
カールしていますね。
まるでリボン細工?の花のよう・・。
風車にも見えますね。
紅紫の長いしべも印象的です。
静岡県西部と、愛知県三河山間部に分布します。
キク科の植物です。
過去記事のハグマの仲間はこちら→モミジハグマ
- Comments: 0
- TrackBacks: 0















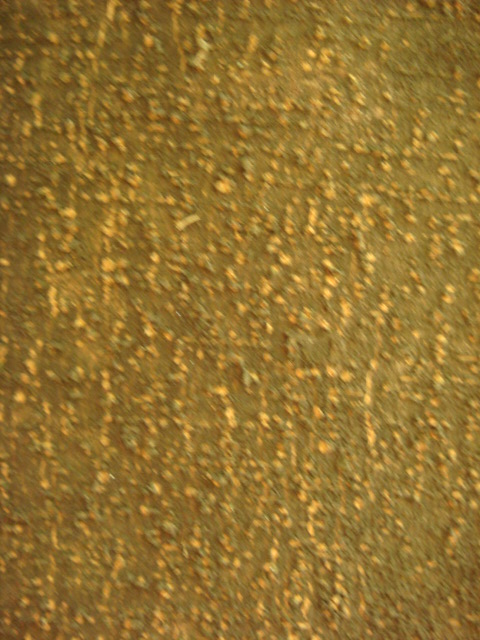

























 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

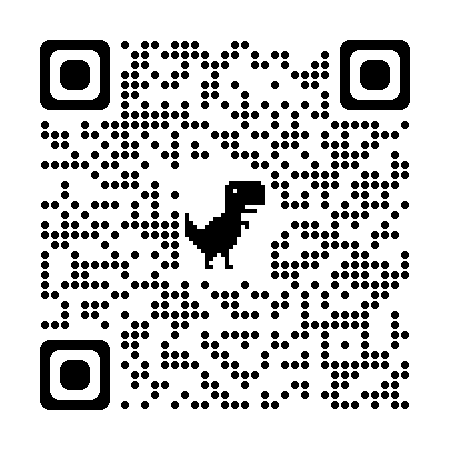 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







