Home > Archives > 2010年10月 Archive
2010年10月 Archive
ミカワマツムシソウ
- 2010年10月30日 17:08
- 花
台風が来ている地方の皆様にはお見舞い申し上げますm(_ _)m。
こちらは台風の進路からはずれたようで、何事もなく一日過ぎようと
しています。
きょうは「ミカワマツムシソウ」をお届けします。
マツムシソウの名の由来は、マツムシが鳴くころに花が咲くという説と、
花が咲き終わったあとに残る坊主頭のような形が松虫鉦(まつむしかね)
とよばれる仏具の形に似ているからという説があるようです。
ちなみに松虫鉦を調べてみましたが・・
ん~|´・_・)゚д゚) ̄_ ̄)・x・) ワカンナイッ...
\(・_\)ソノハナシハ (/_・)/オイトイテっと・・
さて、ミカワマツムシソウ(三河松虫草)の花は
こんなふうでした↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
花が直径1~2センチ程と小さく、マツムシソウ
より小ぶりです。
花の後はこんなふうです↓
これが先述の坊主頭です↑
ツンツン飛び出しているものは針状になったガク片だそうです。
中にはこんなのも混じって咲いていました↓
葉は羽状に深く裂けています。
ミカワマツムシソウはマツムシソウの変種だそうです。
東三河の低山地に分布します。
マツムシソウ科の植物です。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
ヤマハッカ
- 2010年10月29日 12:16
- 花
どんよりとしたお天気です。
台風の影響で、こちらは夜から雨になる模様・・。
さて、山の土手に紫色の花が群生していました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
近寄って見ると、ヤマハッカでした。
きょうは「ヤマハッカ」をお届けします。
「山薄荷」と書きます。
高さは60~90センチ程でした。
茎は四角く、毛が生えています。
葉は向かい合って付いており、縁に粗いギザギザがあります。
葉の表面には毛が生え、裏の葉脈上には毛が多いですね。
薄紫色の花は上の方で4つに分かれ、濃い紫色の
縦の線状の模様があります。
これがヤマハッカの特徴です。
よく似た花にイヌヤマハッカがあります。
舟型の花はキツネの顔に似ていませんか^^。
雄しべは4個ありますね。
ウラナミシジミがやってきました。
北海道~九州の山地に分布します。
シソ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
トキリマメの実
- 2010年10月28日 20:48
- 草の実
秋の雨が静かに降った一日でしたね・・。
きのう京都の和菓子屋の鬼まんじゅうで、鬼まんじゅうの上に甘く
煮た小豆が載っている、変り種の鬼まんじゅうを買って食べました。
まあ、おいしかったけど、私はやはりシンプルな鬼まんじゅうの
方がいいと思いました_(・_.)/ コケッ。
さて、きょうは「トキリマメ」をお届けします。
「吐切豆」と書きます。
名の由来は不明らしい。
別名はオオバタンキリマメというそうです。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
山地や丘陵地の林の縁に生えるつる性の植物です。
葉は3つの小さな葉からなっています。
大変よく似た タンキリマメとの違いは、
葉の付け根寄りに葉の幅のいちばん広いところがあることです。
また、葉は薄く、葉にある毛はまばらなことです。
パッと見、タンキリマメよりトキリマメの葉の方が、バランス的に
スマートな感じを受けます^^。
葉裏はこんなふうでした↓
これから季節が進むと赤いさやが茶色になり、実がはじけて、
中からぶらさがったような黒い種が出てくることでしょう。
関東以西の本州~九州に分布しています。
マメ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
シロオニタケの幼菌
- 2010年10月25日 10:39
- その他
朝からシジュウカラやモズが元気に鳴いています。
おととい、また久しぶりに東三河の山にでかけることができました。
草木に混じってきのこもいくつか見られました。
きょうはきのこを紹介しようと思います。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
いきなりぼよよ~んと目の前に出現したような
強烈なインパクトがありました^^。
「シロオニタケ」の幼菌でした。
見た時は名前は知りませんでしたが、帰宅してPCを開いたところ、
偶然にもきのこ山書房さんのアーカイブから、
すぐに名前がわかりました。
きのこ山さん、どうもありがとうございますm(_ _)m
さて、このきのこは「オニタケ」(鬼茸)という名を
もらっているだけに、傘の表面にトゲトゲ?イボイボ?が
たくさんありますね。
愛嬌のある形の幼菌ですね^^。
方言で、"しろとっくり"ともいわれるそうです。
有毒きのこだそうです。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
コケオトギリ
- 2010年10月21日 12:39
- 花
朝から雨が降ったりしてほとんど日差しのないお天気です。
こちらでは、まだ夏から咲いているサルスベリや、フヨウ、ムクゲ
など咲いていますが、ピラカンサの実もだいぶ赤みを増してきました。
さて、きょうは湿地の周りに咲いていた「コケオトギリ」を
お届けします。
「苔弟切」と書きます。
小型のオトギリソウ(弟切草)なのでコケとついているらしい。
オトギリソウの名前の由来は、いつかオトギリソウをアップする日
まで待っていてくださいね^^;
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
丈は10~30センチ程です。
花びらは5枚です。
雄しべは5~8個あるそうです。
茎は四角張っています。
葉は丸っこく、向かい合って付いており、葉は茎を抱いています。
秋には紅葉するようです。
北海道西南部~九州の湿地や休耕田に生えるそうです。
オトギリソウ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ヘラオモダカ
- 2010年10月18日 08:38
- 花
朝から青く高い空の下、花壇のコスモスが風に揺れていました。
きょうは水湿地に生えていた「ヘラオモダカ」をお届けします。
「箆面高」と書きます。
葉がヘラ状でオモダカのような花を付けるということで名付けられました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
花は径1センチ程の白色で3枚の花びらを付けます。
雄しべ6個と雌しべは多数あります。
緑色の実が付いていました。
ひとつひとつの種には1本の深い溝があります。
北海道~九州の水田や溝、浅い水中に生えます。
オモダカ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ミゾカクシ
- 2010年10月15日 08:09
ベランダで、去年のこぼれ種から芽生えて育った一本だけの
アオジソ に可愛い白い花がいっぱい付きました。
虫食いの葉もいとおしく、小さな透明ガラスの花瓶に挿しました。
きょうは湿地にあった「ミゾカクシ」をお届けします。
「溝隠」と書きます。
別名はアゼムシロ(畦筵)と言います。
湿地や田んぼに生えています。
生育場所と繁殖力の旺盛なことを表していますね。
横から見たところ↓
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
葉は互い違いに付き、やや厚くて柔らかく、長さは1センチ程。
葉の縁にはゆるいギザギザがありますね。
上から見たところ↓
花は1センチ程の大きさですが、花の形は扇形です。
花の先は5裂しています。
この仲間の園芸種が"ロベリア"で、お花屋さんで売られていますね。
北海道~九州に分布します。
キキョウ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ヤブマメ
- 2010年10月11日 15:57
- 花
モズが盛んに鳴いています。
朝から快晴で日差しも強く、戸外の日向は暑いくらいです。
シジュウカラやアゲハ蝶などの姿も見えました。
きょうから我が名古屋でCOP10が開催されています。
今もTVでずーっと特集番組をやっています。
さて、きょうはきのう出かけた先でも見かけた「ヤブマメ」を
お届けします。
「藪豆」と書きます。
文字通り、藪のような所に生えるマメという意味です。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
蔓性で他の植物にからみついて生えています。
林の縁や草原などに生えます。
3枚でひとつの葉を付けており、それは互い違いに付いています。
葉や茎に毛が生えています。
紫青色と白の蝶形の花は、長さ1.5~2センチ程で2個から数個を
まとまって付けています。
実も付いていました↑
平べったくて、長さは2~3センチ程でした。
北海道~九州に分布します。
マメ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ミズオオバコ
- 2010年10月10日 20:25
- 花
皆さん、こんばんは。
連休はいかがお過ごしでしょうか?
私は、きょう2時間程、豊田に取材に出かけることができました^^v
水湿地にあった「ミズオオバコ」をお届けします。
「水大葉子」と書きます。
水の中にあって葉の形がオオバコに似ているため、名付けられました。
昔は田んぼの雑草の一つでしたが、今は激減して貴重な水性植物と
なっており、たまに、ため池や水湿地に生えています。
栄養分が多くて浅い水域に生えることが多いそうです。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
↑3枚の花びらをもつ径2~3センチ程で白色の花です。
うっすらとピンクがかった花色のもあるそうです。
↑花の左には水中にある葉も見えています。
また、花の右上には水から突き出た実も見えていますね。
本州~九州に分布します。
トチカガミ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ハシカグサ
- 2010年10月 6日 19:18
- 花
サクラやケヤキの葉もハラハラと落ち、すっかり秋になりました。
虫の音も心地よく聴こえます。
さて、きょうは「ハシカグサ」をお届けします。
「麻疹草」と書きます。
名の由来は、葉が乾くと赤褐色に変わる様子が、麻疹(はしか)の発疹に
似ているので・・という説があるようですが、はっきりしません。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
小さな壷のような白い花は先が4つに裂けています。
葉は向かい合って付いています。
葉の両面にまばらな毛があり、葉裏は白っぽく見えました。
ガクには密生した毛がありました。
北海道~九州の山野のやや湿った林の中や道端などに生えます。
アカネ科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ヤマハハコ
- 2010年10月 2日 13:44
- 花
十月に入って最初の土曜日、秋らしい良い日和となりました。
皆さん行楽に出かけられたのか? 静かです^^。
隣の雑木林のアベマキが風のそよぎで白い葉裏を見せています。
きっと、もう、丸っこいどんぐりも付けていることでしょう。
さて、きょうは愛読者の要望にお答えし、先回掲載した写真に
写っていた白い花をご紹介しましょう~♪
それは「ヤマハハコ」でした^^。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
「山母子」と書きます。
山にあって、ハハコグサに似ていることから名付けられました。
山の日当たりの良い道端や草地に生えます。
ちょっとドライフラワーっぽい。
高さ30~70センチ程で、細長い葉は互い違いに付いています。
茎や葉は灰緑色に見え、茎や葉の裏には白い綿毛が密生しています。
白い花びらに見えるのは花びらではなく、苞だそうで、
本当の花は中心にある黄色の花です。
本州の中部地方以北~北海道に分布しています。
キク科の植物です。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0




































 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

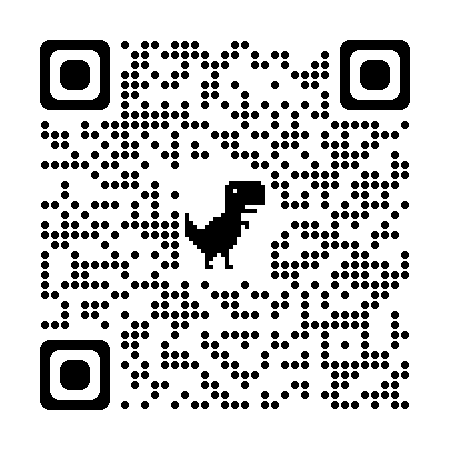 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







