Home > Archives > 2009年5月 Archive
2009年5月 Archive
アメリカキササゲ
- 2009年5月31日 09:46
- 花
雨が降り、窓を閉め切るとなんだか蒸し暑いですね・・。
きょうは在庫の中からのご紹介にします^^;
毎年見るのに花がなかなか撮れなかった「アメリカキササゲ」、
先日やっと撮れたものをお届けします。
「アメリカ木大角豆」と書きます。
果実の形が豆のササゲに似ているので名付けられました。
原産地はアメリカ南部、わが国へは明治末期に渡来したそうです。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
高さ5~12メートル程の落葉高木です。
葉には長い柄があり、向かい合って付いており、先端が短く尖ります。
秋には黄色く紅葉し、どんどん葉が落ちていくので、
その時期には、毎日、落ち葉掃きをしている姿を見かけます。
花はシャンデリアのように付き、綺麗なのですが、
咲いている時期が案外短いです。
遠目には白い花ですが、よく見ると、黄色と紫褐色の班が入っています。
ノウゼンカズラ科の植物です。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
エンシュウムヨウラン
- 2009年5月26日 21:45
五月晴れ、陽が射すところは暑いですが、吹く風は爽やかです。
マンションのサツキも次々と咲いてきて、目にも色鮮やかです^^。
先日、静岡県と愛知県でしか見られないという蘭に出会えたので、
お届けします。
それは「エンシュウムヨウラン」です。「遠州無葉蘭」と書きます。
静岡県西部(遠州)で発見され名付けられました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
名前の通り葉がないので、根に菌を飼って栄養を補給するそうです。
葉緑素を持たない腐生植物です。
ひとつ見つけると、ここそこに十数輪咲いていました。
アリが訪問していました。
たまに木洩れ日が射す程度の薄暗い林の傾斜面にありました。
その腐葉土の中から葉のない、10~20センチ程の焦げ茶色の
細い茎が出ており、地味な黄色(ロウバイの色)の花が咲いていました。
上から写真を撮ってみました。
花は1.5センチ程でした。
花も茎も地味な色で目立たず、よく見ないとスルーしちゃいそうです。
ラン科の植物です。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
ハクウンボク
- 2009年5月22日 12:57
- 花
今にも空が泣き出しそうなお天気ですが、お昼前に
今年4輪めのトケイソウがベランダで咲きました。
さて、きょうは「ハクウンボク」をお届けします。
「白雲木」と書きます。
白い花が鈴なりに咲いている姿を、空にたなびく白雲に
例えて名付けられました。
北海道~九州の山地に生える、高さ 6 ~ 15 メートルの
落葉高木です。
花は房のように咲いています。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
また、花の柄はありますが、少し短めです。
花びらは5裂し、長さ1.8センチ程。雄しべは10本あります。
葉は丸っぽく、互い違いに付いており、裏面はやや白っぽいです。
エゴノキ科の植物です。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ミズキ
- 2009年5月20日 08:08
- 花
きょう、こちら名古屋は真夏日だそうです^^;
きのう、家の近くの大学の前を車で通りかかったところ、
薄紫のセンダンの花がいっぱい咲いているのを見ました。
ホント、夏ですね・・。
ところで、渋谷の金王坂の、とあるビルの敷地の一角にミズキが
3本あるそうですね。
白い花を沢山付けた水平に張る枝ぶりがとても良い眺めだと
出張した時に見た、連れ合いが申します。
私も是非、ミズキを見たいなぁと思っていたら、先日、こちらで
見る機会に恵まれました^^。
ということで、きょうはミズキをお届けします。
「水木」と書きます。
樹液が多く、春先に切ると水が滴り落ちるため、名付けられたそうです。
ミズキ科の落葉高木です。
見たのは10メートル程の木でしたが、カメラに全体が収まらず・・(泣)
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
ミズキの特徴は、枝が横に張り、階段状の特異な樹形をしていることです。
葉は互い違いに付いており、葉先は尖っています。
葉の表面は深緑色で裏は白っぽい。
白い小花が集まって付いています。
花びらは4枚で雄しべも4本です。
北海道から九州の山腹の緩やかな斜面や川原等に分布します。
日向を好み、生長が速い木だそうです。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
アイラトビカズラ
- 2009年5月17日 17:49
- 花
きょうは、先日、東山植物園で撮った珍しいものをお届けします。
植物園の坂道を降りてきたら、足元に見慣れぬ花のようなものが
びっしりと落ちていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
上を仰いでびっくり!いきなり目の前にジャングルが・・。
そして、太いつるにいっぱいブドウのように垂れ下がっていました。
(写真をいっぱい撮ったのですが、スケールが大きすぎ、どれもイマイチ・・
うまく伝えられないかも?どうぞ、ご勘弁を・・。)
正体は「アイラトビカズラ」でした!
「相良飛蔓」と書きます。
熊本県山鹿市菊鹿町相良(あいら)に自生するトビカズラということです。
樹齢は推定1000年で、国の指定特別天然記念物となっているそうです。
源平の乱で相良寺が焼きうちにされたとき、千手観音がこのカズラに飛び移り
無事だったという伝説から、「アイラトビカズラ」と名付けられたそうです。
葉は三つでひとつの葉になってます。
太い幹から緑色の茎を伸ばし、その先に7センチ程の暗赤紫色の大きな
蝶形の花を藤のように房状に付けています。
十数個もぶら下がっているのもありました。
まるで巨峰ブドウの房のようでもあります。
マメ科の常緑のつる性植物です。
撮影中もひっきりなしにボタッ、ボタッと音をたてて落花していました。
しばし、南国の迷宮に迷いこんだ心もちでたたずんでいました。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
サイカチ
- 2009年5月15日 15:22
- 花
きのう、きょうと立て続けに「トケイソウ」が咲きました。
でも、きょうは幹や枝に鋭い棘がある「サイカチ」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
すごい棘でしょ!とっても痛いっ!
サイカチの棘は、枝が変形したものです。
ちょうど、花も咲いていました。
マメ科の植物です。
葉を見ると明らかにマメ科の植物ですが、花はマメ科の特徴である
蝶の形をしていません。
調べたら、マメ科の中では最も原始的な木だからだそうです。
花は房状になっていて、長さは見たところ数センチ~10センチ程でした。
花びらは4枚でした。
サイカチの名前の由来は、古名の西海子(さいかいし)からきたらしい。
「皀莢(そうきょう)」ともいうそうです。
マメ科の高木で落葉します。
本州中南部、四国、九州に分布しているそうです。
山野の他、別名を「カワラフジノキ」というように、川岸など
水辺にも生えているそうです。
若葉はゆでで食用になり、莢は洗剤として利用できるそうです。
種や棘は薬用に利用されるそうです。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ミツバの花
- 2009年5月12日 09:40
- 花
先日、お友達の庭で丹精込めて作られた土付きのミツバを
いただきました。
植木鉢に植えておいたら、根付きました。
山では6月頃から花が咲くそうですが、これは園芸種なのか、
数日前からもう花が咲きました。
初めて花を見ましたので、きょうはこの「ミツバの花」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
「三葉」と言うとおり、葉が三つに分かれています。
葉は互い違いに付いていて、縁には不揃いなギザギザがあります。
大きさ2ミリ程のごく小さな白い花で、花びらは5枚です。
とても清楚な感じがします。
日本原産で、北海道~九州に分布します。
セリ科の植物です。
三つ葉はとても香りが良く、野菜として栽培もされますね。
さっそく茎葉をいただきましたが、季節の味でとてもおいしかったです^^。
- Comments: 6
- TrackBacks: 0
アズキナシの花
- 2009年5月10日 09:58
- 花
きのうから初夏本番になったようです^^。
お日様の下では暑く、日陰に入ると涼しく、気持ち良く感じます。
さて、きょうは先日撮った「アズキナシ」の花をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
直径1.5センチ程の白い花を多数付けます。
葉には規則的な葉脈があり、縁には不規則なギザギザがあります。
雄しべは20本で、雌しべは2本あります。
過去記事も是非合わせてご覧いただくと、よくわかるかと思います。
↓
アズキナシの実
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
オオバウマノスズクサ
- 2009年5月 8日 08:42
- 花
程よく草刈がされた里山にジャコウアゲハがヒラヒラしていました。
ウマノスズクサがあるかもしれないと連れ合いが言うので、
葉に気をつけて見ていきましたが、何時間経っても見つからず・・。
午後4時半をまわり、帰り道でもう一度、最初のぞいた所で、
ついに「オオバウマノスズクサ」を見つけることができました!
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
「オオバウマノスズクサ」はウマノスズクサとともに、
ジャコウアゲハの食草だそうです。
「大葉馬の鈴草」と書きます。
大きい葉を持つ"馬の鈴草"ということで、名付けられました。
中心がへこみ、三つの耳があるような上のような葉の形のもありました。
葉の大きさは8~15センチ程でした。
花は4~5センチ程で、とても個性的!
チューバやサクソフォーンのような形をしています♪
前から見た顔です^^。
花びらはなく、ガク片が筒状に合着しています。
ガク筒には毛が生えていました。
穴?の中まで豹紋模様が付いていましたが、今回はその中までは
見ることができませんでした^^;
↑後ろ姿です。
↑蕾もありました。毛に覆われていますね。
茎はつる状で、笹に絡みついていました。
まだ緑色のつるでしたが、調べたら、木化するそうです。
また、根元には同じ科のカンアオイがありました。
ウマノスズクサ科の植物です。
関東以西、四国、九州に分布しているそうです。
- Comments: 6
- TrackBacks: 0
ワチガイソウ
- 2009年5月 6日 20:24
- 花
いつもご愛読いただき、有難うございます。
お蔭様でこの五月でfabも5年目に入りました。
きょうまで続けてこられたのも、皆様のお蔭と感謝しております。
これからもどうかよろしくお願いします。
さて、きょうは「ワチガイソウ」をお届けします。
「輪違草」と書きます。
だあれ?マチガイソウと間違えそう?なんて・・笑
ブナ林の渓流のそばに生えていました。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
星形の花の花びらは5枚。
雄しべは10本で、黒い葯がアクセントになっています。
葉は向かい合ってついています。
茎は細く、直立して枝分かれせず、毛があります。
福島県以南の本州、四国、九州に分布しているそうです。
ナデシコ科の植物です。
- Comments: 4
- TrackBacks: 0
カナビキソウ
- 2009年5月 5日 09:25
- 花
朝から雨ですね~。
連休もあと少し、皆様いかがお過ごしでしょうか?
きょうは、先日、里山で見つけた小さな星形の白い花、
「カナビキソウ」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
「鉄引草」と書きますが、名の由来はよくわかりません。
葉は細く線のようで互い違いに付いています。
花は葉の脇にひとつ付き、数ミリとごく小さい。
白く花びらのように見えるのはガクだそうです。
北海道南部、本州、四国、九州、沖縄に分布しているそうです。
日当たりの良い道端に生えていました。
調べたら、自身も葉緑素を持って光合成を行うが、
他の植物からも栄養をとる半寄生植物らしいです。
ビャクダン科の植物です。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
ハナイカダの花
- 2009年5月 4日 10:56
- 花
先日、3年ぶりにやっと「花」が撮れたので、お約束どおり
「ハナイカダの花」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
雌雄異株で、これは雌株のようです。
葉の上に1個の雌花を付けています。(2個のもあります。)
北海道以南の林縁に自生しています。
過去記事でハナイカダの実を取り上げているので、
是非、合わせてご覧ください。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
コチャルメルソウ
- 2009年5月 3日 08:54
県内にあるバードシャワーで有名な山に行く途中の渓流沿いで、
「コチャルメルソウ」と出会いました。
「小哨吶草」と書きます。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
花びらは5枚あり、魚の骨のよう・・。
1枚の羽状の花びらは、9つに切れ込んでいるもようです。
葉は緑色で浅くギザギザがあり、葉の両面には粗い毛が
こんなふうに生えていました。
雄しべは5つ、雌しべはひとつでした。
実はこんなふうでした。
本州、四国、九州に分布しているそうです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ミカワチャルメルソウの実
- 2009年5月 2日 13:14
- 草の実
一週間のご無沙汰でした。
あっという間に季節が進み、ゴールデンウィークまっ只中!
皆様いかがお過ごしでしょうか?
私はミカワチャルメルソウの実を探してきましたヨ。
きょうはその「ミカワチャルメルソウの実」をお届けします。
(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)
もう、魚の骨のような花びらはなくなっていました。
中はこんなふうになっていました。
実の形、チャルメラの形だったよね。
- Comments: 2
- TrackBacks: 0























































 Apple Store にて公開中です
Apple Store にて公開中です

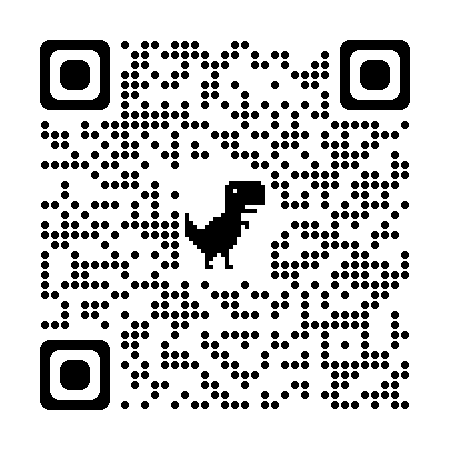 GooglePlay にて公開中です
GooglePlay にて公開中です
 ☆むしふぁぶ☆
☆むしふぁぶ☆







